7月8日放送分_「飛騨の鶏ちゃんとトンチャン」について
(7月8日放送分 第204回)みなさんこんにちは。飛騨の歴史再発見のコーナーです。
このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。
それにしても毎日暑いですねえ。もう七月に入りましたが、先月は各地で6月としては
最高気温を記録したところもあったようです。
今年の夏は、福島原発事故の影響で、全国の原子力発電所が休止するのか、それとも再開
するのか、物議を醸しだしています。調べてみますと、日本の全電力エネルギーのうち、
原子力発電に頼っているものが、全体の12%ほどというデータが有ります。
この12%という数字は、年間を通してのお話ですが、今一番電力を使う季節がこれから
迎えようとしている夏です。自動車社会になって、化石燃料を燃やすことが多くなり、
大量の二酸化炭素が排出されるようになりました。
そこに加えて情報化社会になって、パソコンなどの利用率がものすごく上昇し、そういった
ものや家電から発せられる熱があるために、ビルなどの建物内ではクーラーを利用すること
が多くなったので、室外機から発せられる熱がどんどん外に出されます。
おまけに、道路を舗装するようになって、雨の浸透がなくなり、気化熱で地表の熱が奪われる
ことが少なくなったために、アスファルト自体が熱を持つようになりました。
そういった相乗効果が働き、最近の日本でも砂漠地帯と同じくらいの気温を観測することが
多くなってきています。
先ほど申し上げましたように、全体的には12%ですが、理論上は火力発電を増加させれば
賄える量だと言われていますが、火力発電を増加させると今度は二酸化炭素が増加する。
そこで、なるべく節電をして使用量を減らそうと云う運動と、自然エネルギーを電気に変える
ことを考えようと云う動きが広まっております。
たとえば、風力ですとか、波の力を利用した発電。そして最近は、ダムの水を夜中にいったん
上の池に上げて発電する揚力発電。太陽光を使った太陽光発電などの発電所が、最近全国に
作られてきました。
しかし最近は、温度差とか標高差とか少しでも“差”が有れば発電が出来ると云うので、
最近はいろんな差を求めて発電の研究がなされているようです。
実際に、小川や家の前の溝のような小さな流れでも家の電灯分くらいは発電できるシステムが
現在は有るようです。
皆様も、身の周りのエコについて、節電について、今一度考えてみてはいかがでしょうか。
さて、前置きが長くなりましたが、本日の放送に入りましょう。
本日の放送は、先週下呂市萩原町で、「全日本鶏ちゃんで笑えフェスティバル」というイベント
が行われました。
その時に発表された内容で面白いお話が有りましたので、飛騨の歴史再発見風にお届けしたいと
思います。
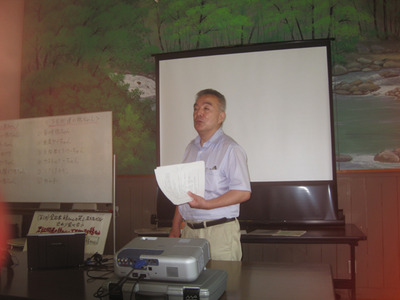
実は、このイベントは、私の大学の先輩の長尾さんが企画されたものですが、岐阜県の南飛騨を
中心にして、広まっている「鶏ちゃん」の食文化を見直そうと開催されたものです。
その目的に書かれているものを読みますと
「鶏ちゃんを味わいながら鶏ちゃん風土と鶏ちゃん産業を探り、新しいケイちゃん文化を進化
させようというもの。さらには鶏ちゃんに合うであろう一品を添えることで新たな鶏ちゃんの
楽しみ方を提案し、鶏ちゃんを囲む陽気な笑いを全国へ発信する。」といったものです。
今回の企画のメインは、「下呂の鶏ちゃんvs郡上の鶏ちゃん」という事で、どちらがおいしい
か。どのように味が違うかということを味比べしようと云うものでした。
今回は、第1回目という事で、これから拡大していきたいと云うお話でした。

実は私も、この番組をやっている人だから味の審査員として参加してほしいと、このほど審査員
に任命され、イベントに参加してまいりました。
萩原町の山之口にある位山交流館の食堂にて開催されたのですが、どれもこれもおいしいもの
ばかりで、なかなか判定ができませんでした。
実際に食べてみて、現在はたくさんの種類の鶏ちゃんがあるということを再認識しましたし、
どれも各店舗の工夫が凝らされていて、本当にいろんな鶏ちゃんがあるんだなということに
感心しました。
後半では、鶏ちゃんの歴史についてや、今回のイベントについて、もう少し詳しくお話
しましょう。
ちょっとここでブレイクしましょう。
曲の方は。「ザビレッジシンガーズ 亜麻色の髪の乙女」をお届けします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
本日の飛騨の歴史再発見は「鶏ちゃんで笑えフェスティバル」についてお話しています。
この「鶏ちゃん」、最近では南飛騨の下呂市が発祥地だとして、いろんなお店が「うちが
元祖です」という看板を掲げて宣伝されています。
TV番組にも取り上げられて、下呂市が一大発祥地のような観が有ります。
ところが、お隣の郡上市にも、この「鶏ちゃん」の元祖のお店がたくさんあったり、
高山でも荘川地区にあったり、最近でしょうが、焼き肉屋さんや居酒屋にも定番のメニュー
となったりしています。
お土産屋さんでも冷凍パックで売られたりしていて、結構人気の商品となってきています。

おそらく、岐阜県の南飛騨近辺で考えだされた商品であるには間違いないのですが、今回
その歴史を考え、また、味比べをしようというイベントでした。
全体的な特徴としては、郡上のものは、豆味噌系を使ったものが多く、最近は親鳥も混ざる
ケースも出てきているという感じでした。
一方、下呂のものは、圧倒的に醤油系で、若鳥を使ったものがほとんどという感じでした。
それぞれ、特徴が有りますが、どちらもおいしく頂きました。
さて、こんなに元祖がたくさんあっては、いったいどこが発祥なのか解らないと、長尾先輩が
かつてから疑問に思っておられまして、お調べになられました。
そもそも、鶏ちゃんというのは、郡上から神岡にかけての鉱山労働者が家庭料理として食べて
いたものらしく、ホルモンを中心にしたトンチャンと同じ系統のものが発祥ではないかという
事でした。
ただし、一つはっきりしたことは、最初の商品化は萩原の肉屋さんが昭和34年に開発された
商品だと云う事がわかりました。意外と新しい商品なんですね。
そこで、長尾さんは、今年になって岐阜県庁の食堂でワンコイン弁当を開発され、鶏ちゃんの
歴史を物語にして包装紙に書いて広めることにしました。
以下、そこに書かれていることを御紹介したいと思います。
これは、ましたの絵本~いただきます鶏ちゃん物語~に2009年に紹介されていた内容です。
「それは昭和34年の事、飛騨萩原の小さな肉屋さんの店頭に「味付けかしわ」で登場したのが
「鶏ちゃん」商品の始まりだ。
精一杯の生活の中からひらめき作り上げた、感謝にあふれる天の恵みの味です。
20代の若き女将は、自転車の後ろの両側へ振り分けカゴを取り付け、フウフウと荒い息を吐き
ながら、川沿いのデコボコ道や峠を越えたりして、鶏が飼われている農家を探しまわった。
青い草がいっぱい生える広い庭を、コッココッコと元気に動き回り、土からミミズを掘出し、
食べている姿に出会う。表情豊かな鶏たちのまさに楽園だ。
「あいつとこいつはいい」と鶏舎の主人が案内する。必死に一羽を抱きかかえ、藁で足をクルッ
と縛り、自転車のかごに入れていく。
五羽ほどが入り一杯になり、帰りの自転車はとても重くて、汗だらけの体で店に戻る。
大きなお釜に湯を一杯わかし、絞めた鶏を突っ込めば、ボロボロと羽がむしれてしまう。
きれいに丸裸になった一羽一羽を竹串に吊るしていく。農家で仕入れた鶏は、運動量が豊富で
とても健康だ。
こんなに良質な鶏肉を、早く皆に食べてもらいたい。考えたのが日持ちさせるためにも味を
付けることだった。
村の家々にある自家製の味噌・醤油を基本に、七味やゴマなどいろいろ混ぜたりして、鶏肉に
味を付けた。
だから商品名も「味付けかしわ」だ。
やさしい味に村人たちが買い求めた。いつしか「鶏ちゃん」と呼ばれるようになり、商品名も
「鶏ちゃん」になった。」というような内容です。
一方で、最近神岡でトンチャンを使った町おこしが行われていますので、ちょっと調べてみま
したのでご紹介いたします。

神岡商工会議所の方のお話では、
「昭和10年頃、神岡鉱山で働く朝鮮系労働者が、高価な肉の代わりにホルモンを食べた。
その時には、鉄板の代わりに作業で使ったスコップの上でホルモンを焼いていた。
その後、戦時中に神岡町西里の現在富銀のある場所にて、田河屋が創業。飲食店での提供が
始まるが、その頃はまだ、七輪の上に網デッキとセメント紙を敷いて提供するだけのもの
だった。
戦後、とんちゃんという名前が少しずつ浸透しはじめるが、注意すべきは、鶏ちゃんは鶏の
モツだが、とんちゃんは豚のモツではなく、朝鮮ではとんが排泄物、ちゃんが腸、のような
意味で名付けられている。
また、神岡町のとんちゃんは牛のホルモンであり、内臓は飛騨牛と名乗ることが出来ないが、
飛騨牛の内臓を使っている。」ということでした。
さあ、ビールの季節です。今日のお話を思い出して、スタミナをいっぱいつけて下さいね。
さて、本日も時間となりました。
来週は廣瀬氏について、先日長浜に行って調べてきたお話をしたいと思います。
本日はこの曲でお別れです。
曲は「竹内まりあ プラスティックラブ」をお届けします。また来週、お会いしましょう!
このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。
それにしても毎日暑いですねえ。もう七月に入りましたが、先月は各地で6月としては
最高気温を記録したところもあったようです。
今年の夏は、福島原発事故の影響で、全国の原子力発電所が休止するのか、それとも再開
するのか、物議を醸しだしています。調べてみますと、日本の全電力エネルギーのうち、
原子力発電に頼っているものが、全体の12%ほどというデータが有ります。
この12%という数字は、年間を通してのお話ですが、今一番電力を使う季節がこれから
迎えようとしている夏です。自動車社会になって、化石燃料を燃やすことが多くなり、
大量の二酸化炭素が排出されるようになりました。
そこに加えて情報化社会になって、パソコンなどの利用率がものすごく上昇し、そういった
ものや家電から発せられる熱があるために、ビルなどの建物内ではクーラーを利用すること
が多くなったので、室外機から発せられる熱がどんどん外に出されます。
おまけに、道路を舗装するようになって、雨の浸透がなくなり、気化熱で地表の熱が奪われる
ことが少なくなったために、アスファルト自体が熱を持つようになりました。
そういった相乗効果が働き、最近の日本でも砂漠地帯と同じくらいの気温を観測することが
多くなってきています。
先ほど申し上げましたように、全体的には12%ですが、理論上は火力発電を増加させれば
賄える量だと言われていますが、火力発電を増加させると今度は二酸化炭素が増加する。
そこで、なるべく節電をして使用量を減らそうと云う運動と、自然エネルギーを電気に変える
ことを考えようと云う動きが広まっております。
たとえば、風力ですとか、波の力を利用した発電。そして最近は、ダムの水を夜中にいったん
上の池に上げて発電する揚力発電。太陽光を使った太陽光発電などの発電所が、最近全国に
作られてきました。
しかし最近は、温度差とか標高差とか少しでも“差”が有れば発電が出来ると云うので、
最近はいろんな差を求めて発電の研究がなされているようです。
実際に、小川や家の前の溝のような小さな流れでも家の電灯分くらいは発電できるシステムが
現在は有るようです。
皆様も、身の周りのエコについて、節電について、今一度考えてみてはいかがでしょうか。
さて、前置きが長くなりましたが、本日の放送に入りましょう。
本日の放送は、先週下呂市萩原町で、「全日本鶏ちゃんで笑えフェスティバル」というイベント
が行われました。
その時に発表された内容で面白いお話が有りましたので、飛騨の歴史再発見風にお届けしたいと
思います。
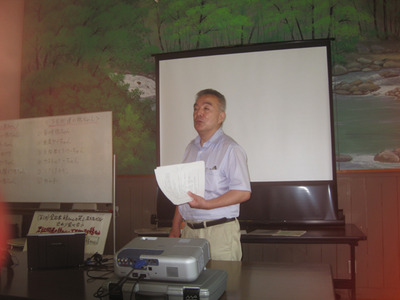
実は、このイベントは、私の大学の先輩の長尾さんが企画されたものですが、岐阜県の南飛騨を
中心にして、広まっている「鶏ちゃん」の食文化を見直そうと開催されたものです。
その目的に書かれているものを読みますと
「鶏ちゃんを味わいながら鶏ちゃん風土と鶏ちゃん産業を探り、新しいケイちゃん文化を進化
させようというもの。さらには鶏ちゃんに合うであろう一品を添えることで新たな鶏ちゃんの
楽しみ方を提案し、鶏ちゃんを囲む陽気な笑いを全国へ発信する。」といったものです。
今回の企画のメインは、「下呂の鶏ちゃんvs郡上の鶏ちゃん」という事で、どちらがおいしい
か。どのように味が違うかということを味比べしようと云うものでした。
今回は、第1回目という事で、これから拡大していきたいと云うお話でした。

実は私も、この番組をやっている人だから味の審査員として参加してほしいと、このほど審査員
に任命され、イベントに参加してまいりました。
萩原町の山之口にある位山交流館の食堂にて開催されたのですが、どれもこれもおいしいもの
ばかりで、なかなか判定ができませんでした。
実際に食べてみて、現在はたくさんの種類の鶏ちゃんがあるということを再認識しましたし、
どれも各店舗の工夫が凝らされていて、本当にいろんな鶏ちゃんがあるんだなということに
感心しました。
後半では、鶏ちゃんの歴史についてや、今回のイベントについて、もう少し詳しくお話
しましょう。
ちょっとここでブレイクしましょう。
曲の方は。「ザビレッジシンガーズ 亜麻色の髪の乙女」をお届けします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
本日の飛騨の歴史再発見は「鶏ちゃんで笑えフェスティバル」についてお話しています。
この「鶏ちゃん」、最近では南飛騨の下呂市が発祥地だとして、いろんなお店が「うちが
元祖です」という看板を掲げて宣伝されています。
TV番組にも取り上げられて、下呂市が一大発祥地のような観が有ります。
ところが、お隣の郡上市にも、この「鶏ちゃん」の元祖のお店がたくさんあったり、
高山でも荘川地区にあったり、最近でしょうが、焼き肉屋さんや居酒屋にも定番のメニュー
となったりしています。
お土産屋さんでも冷凍パックで売られたりしていて、結構人気の商品となってきています。

おそらく、岐阜県の南飛騨近辺で考えだされた商品であるには間違いないのですが、今回
その歴史を考え、また、味比べをしようというイベントでした。
全体的な特徴としては、郡上のものは、豆味噌系を使ったものが多く、最近は親鳥も混ざる
ケースも出てきているという感じでした。
一方、下呂のものは、圧倒的に醤油系で、若鳥を使ったものがほとんどという感じでした。
それぞれ、特徴が有りますが、どちらもおいしく頂きました。
さて、こんなに元祖がたくさんあっては、いったいどこが発祥なのか解らないと、長尾先輩が
かつてから疑問に思っておられまして、お調べになられました。
そもそも、鶏ちゃんというのは、郡上から神岡にかけての鉱山労働者が家庭料理として食べて
いたものらしく、ホルモンを中心にしたトンチャンと同じ系統のものが発祥ではないかという
事でした。
ただし、一つはっきりしたことは、最初の商品化は萩原の肉屋さんが昭和34年に開発された
商品だと云う事がわかりました。意外と新しい商品なんですね。
そこで、長尾さんは、今年になって岐阜県庁の食堂でワンコイン弁当を開発され、鶏ちゃんの
歴史を物語にして包装紙に書いて広めることにしました。
以下、そこに書かれていることを御紹介したいと思います。
これは、ましたの絵本~いただきます鶏ちゃん物語~に2009年に紹介されていた内容です。
「それは昭和34年の事、飛騨萩原の小さな肉屋さんの店頭に「味付けかしわ」で登場したのが
「鶏ちゃん」商品の始まりだ。
精一杯の生活の中からひらめき作り上げた、感謝にあふれる天の恵みの味です。
20代の若き女将は、自転車の後ろの両側へ振り分けカゴを取り付け、フウフウと荒い息を吐き
ながら、川沿いのデコボコ道や峠を越えたりして、鶏が飼われている農家を探しまわった。
青い草がいっぱい生える広い庭を、コッココッコと元気に動き回り、土からミミズを掘出し、
食べている姿に出会う。表情豊かな鶏たちのまさに楽園だ。
「あいつとこいつはいい」と鶏舎の主人が案内する。必死に一羽を抱きかかえ、藁で足をクルッ
と縛り、自転車のかごに入れていく。
五羽ほどが入り一杯になり、帰りの自転車はとても重くて、汗だらけの体で店に戻る。
大きなお釜に湯を一杯わかし、絞めた鶏を突っ込めば、ボロボロと羽がむしれてしまう。
きれいに丸裸になった一羽一羽を竹串に吊るしていく。農家で仕入れた鶏は、運動量が豊富で
とても健康だ。
こんなに良質な鶏肉を、早く皆に食べてもらいたい。考えたのが日持ちさせるためにも味を
付けることだった。
村の家々にある自家製の味噌・醤油を基本に、七味やゴマなどいろいろ混ぜたりして、鶏肉に
味を付けた。
だから商品名も「味付けかしわ」だ。
やさしい味に村人たちが買い求めた。いつしか「鶏ちゃん」と呼ばれるようになり、商品名も
「鶏ちゃん」になった。」というような内容です。
一方で、最近神岡でトンチャンを使った町おこしが行われていますので、ちょっと調べてみま
したのでご紹介いたします。

神岡商工会議所の方のお話では、
「昭和10年頃、神岡鉱山で働く朝鮮系労働者が、高価な肉の代わりにホルモンを食べた。
その時には、鉄板の代わりに作業で使ったスコップの上でホルモンを焼いていた。
その後、戦時中に神岡町西里の現在富銀のある場所にて、田河屋が創業。飲食店での提供が
始まるが、その頃はまだ、七輪の上に網デッキとセメント紙を敷いて提供するだけのもの
だった。
戦後、とんちゃんという名前が少しずつ浸透しはじめるが、注意すべきは、鶏ちゃんは鶏の
モツだが、とんちゃんは豚のモツではなく、朝鮮ではとんが排泄物、ちゃんが腸、のような
意味で名付けられている。
また、神岡町のとんちゃんは牛のホルモンであり、内臓は飛騨牛と名乗ることが出来ないが、
飛騨牛の内臓を使っている。」ということでした。
さあ、ビールの季節です。今日のお話を思い出して、スタミナをいっぱいつけて下さいね。
さて、本日も時間となりました。
来週は廣瀬氏について、先日長浜に行って調べてきたお話をしたいと思います。
本日はこの曲でお別れです。
曲は「竹内まりあ プラスティックラブ」をお届けします。また来週、お会いしましょう!


