HOME › 飛騨の提灯アラカルト
提灯のイベントが行われています
現在、古い町並みでは、古い町並みに提灯を灯すイベントが開催中です。

州さきさん前の細長提灯
このイベントは、冬の高山の観光客を増加させようと、旅館組合青年部が昨年から
企画しているものです。
古い町並みに、提灯を灯し、各旅館に宿泊されているお客様に実際に歩いてもらい、
冬の高山の雰囲気を味わってもらおうと、開催されています。

昨日の天候は、あいにくの大雪となりましたが、旅館組合の方々が、白に闘鶏楽の
模様を刷り込んだ法被を着て、観光客の皆さんを誘導しておられました。
徳積善太
州さきさん前の細長提灯
このイベントは、冬の高山の観光客を増加させようと、旅館組合青年部が昨年から
企画しているものです。
古い町並みに、提灯を灯し、各旅館に宿泊されているお客様に実際に歩いてもらい、
冬の高山の雰囲気を味わってもらおうと、開催されています。
昨日の天候は、あいにくの大雪となりましたが、旅館組合の方々が、白に闘鶏楽の
模様を刷り込んだ法被を着て、観光客の皆さんを誘導しておられました。
徳積善太
錦山神社の提灯アラカルト2
錦山神社の提灯についてお知らせします。今日は、各町内の提灯です。
最初に、春日町の提灯。

お宮や屋台に使われる鏡を表しています。

こちらは、旧日影町(現在の春日町 大隆寺側)のところの提灯です。
この提灯を見て、思いだしたのは、秋の高山祭りの下一之町~寺内町の提灯と同じことです。
「味楽」と書いてありますが、意味については調査中です。
なぜ、下一之町のと同じなのかは、わかりません。もともとそこの組の方が引っ越されたのでしょうか。
ご参考までに、布袋台の提灯を表示します。

どうです、同じでしょう。
つづいて島川原町。

隣同士で、提灯が異なりますが、これは、島川原町と春日町の境目かもしれません。
ただし、一軒だけ提灯が違うので、おそらく、個人で出されたものでしょう。


島川原町の提灯は、春日町の提灯と同じ、鏡です。
これについて、関係者の方にお聞きしたところ、「昔この区域は高山の56区になっていたので、その
なごりで、提灯が同じなのではないか」とのことでした。
さて、いよいよ、最も提灯のバリエーションが富んだ「堀端町」にまいります。

堀端町1 「明輝」と書いた提灯。堀端町の通り沿い。


堀端町2 桜型の模様の入った提灯。堀端町の護国神社前の通り沿い。


堀端町3 堀端町の裏通りから江名子川にかけての一帯。「献燈」

堀端町4 堀端町の裏通りのところの提灯。鏡ですが、模様が入っています。
堀端町の提灯が異なる事について、地元の方にお聞きした処、どうも班ごとに異なっているようです。
これは、昔、錦山神社の祭礼区域が、火消し組の「東組」だったことと関係あるようで、今でも消防組
が○○分団の第△班となっているように、火消し組の班がわかれていたことによるようです。
なお、桜のマークがありましたが、確か、今の消防のマークは「桜模様」でしたよね。同じです。
最後に、宗猷寺町。



宗猷寺町の宗猷寺下の通りの提灯は、すべて同じですが、傘が異なります。
提灯には、「暉昱」(キイク)=かがやきがあきらかなこと だと思いますが、字体からすると日聿のようにも見えます。
これについては、ご存知の方がありましたらお知らせください。
最後に、私が最も気に入っている提灯。

これは、同じ宗猷寺町の中でも、東橋の東詰の一角、数えてみたら4軒だけがこの提灯です。
この意味が解らないのですが、「適意於国骵」とはどのような意味なのでしょうか。
現在調査中です。もしご存知の方ありましたら、お知らせください。いろいろ聞きましたがわかりません。
徳積善太
最初に、春日町の提灯。
お宮や屋台に使われる鏡を表しています。
こちらは、旧日影町(現在の春日町 大隆寺側)のところの提灯です。
この提灯を見て、思いだしたのは、秋の高山祭りの下一之町~寺内町の提灯と同じことです。
「味楽」と書いてありますが、意味については調査中です。
なぜ、下一之町のと同じなのかは、わかりません。もともとそこの組の方が引っ越されたのでしょうか。
ご参考までに、布袋台の提灯を表示します。
どうです、同じでしょう。
つづいて島川原町。
隣同士で、提灯が異なりますが、これは、島川原町と春日町の境目かもしれません。
ただし、一軒だけ提灯が違うので、おそらく、個人で出されたものでしょう。
島川原町の提灯は、春日町の提灯と同じ、鏡です。
これについて、関係者の方にお聞きしたところ、「昔この区域は高山の56区になっていたので、その
なごりで、提灯が同じなのではないか」とのことでした。
さて、いよいよ、最も提灯のバリエーションが富んだ「堀端町」にまいります。
堀端町1 「明輝」と書いた提灯。堀端町の通り沿い。
堀端町2 桜型の模様の入った提灯。堀端町の護国神社前の通り沿い。
堀端町3 堀端町の裏通りから江名子川にかけての一帯。「献燈」
堀端町4 堀端町の裏通りのところの提灯。鏡ですが、模様が入っています。
堀端町の提灯が異なる事について、地元の方にお聞きした処、どうも班ごとに異なっているようです。
これは、昔、錦山神社の祭礼区域が、火消し組の「東組」だったことと関係あるようで、今でも消防組
が○○分団の第△班となっているように、火消し組の班がわかれていたことによるようです。
なお、桜のマークがありましたが、確か、今の消防のマークは「桜模様」でしたよね。同じです。
最後に、宗猷寺町。
宗猷寺町の宗猷寺下の通りの提灯は、すべて同じですが、傘が異なります。
提灯には、「暉昱」(キイク)=かがやきがあきらかなこと だと思いますが、字体からすると日聿のようにも見えます。
これについては、ご存知の方がありましたらお知らせください。
最後に、私が最も気に入っている提灯。
これは、同じ宗猷寺町の中でも、東橋の東詰の一角、数えてみたら4軒だけがこの提灯です。
この意味が解らないのですが、「適意於国骵」とはどのような意味なのでしょうか。
現在調査中です。もしご存知の方ありましたら、お知らせください。いろいろ聞きましたがわかりません。
徳積善太
錦山神社の提灯アラカルト1(神社編)
祭りも終わってしまいましたが、本日は、5月5日に開催された、錦山神社の提灯について
お話したいと思います。
錦山神社祭礼区域 錦町、宗猷寺町、堀端町、島川原町、春日町、旧日影町(春日町)の
区域が祭礼区域です。結構広い区域となっています。今回は、神社関係の提灯が主体です。


錦山神社参道の提灯 錦山神社入り口と階段のところです。文字は「錦山神社」

神社拝殿前の提灯。金森家の「梅鉢紋」となっています。
これについては、金森家二代可重が、慶長年間に錦山神社に稲荷社を勧請し、飛騨の
稲荷社の惣社としたことに由来しています。

錦町への入り口のところの提灯。

錦町と宗猷寺町の境目、酒屋さんのところの提灯。
この場所は、江名子町がここまできているために、複雑な場所が境目となっています。
(塩谷酒店のところは宗猷寺町。その横は江名子町となっています。)

錦町入り口、山本家裏の道の所です。
なぜか、無記名の提灯となっています。場所的にここに提灯があるのは不自然です。

錦山神社参道下の提灯。
江名子との境目に提灯があります。この提灯より神社側は錦町の新興住宅地域です。
かつて、私の小学校の時は、このあたりは田んぼでした。


宗猷寺町入り口の提灯。「御神燈」です。
基本的にこの場所は、愛宕神明神社との境になるはずなのですが、このような提灯になっており、
宗猷寺町と錦町の境目に神社の幟が揚げられています。不思議です。

このように、宗猷寺町の一番奥の所に幟があります。
これは、祭礼区域が昔と異なったのでしょうか。非常に謎です。

春日町入り口の幟旗。
実際には、現在の春日町の区域はもっと広く、ここから大隆寺側の山手にかけても春日町です。
これは、昭和16年の字と町名改正のときに、春日町に入れられた「日影町」という区域です。

護国神社下、島川原町と堀端町の境目の幟旗。お堀の東側。
ここに境目をあらわす幟があるのも不自然で、実際には、馬場町と堀端町の境目にあるべきです。
しかし、場所の関係で、この場所に設置されているものなのでしょう。

錦山神社の北側に鎮座される、錦山稲荷社の提灯。


春日町の秋葉様。提灯に神様の名前があります。

堀端町の秋葉様。こちらの提灯も独特のものです。
なお、島川原町秋葉様、宗猷寺町秋葉様については、撮り忘れました。
徳積善太
お話したいと思います。
錦山神社祭礼区域 錦町、宗猷寺町、堀端町、島川原町、春日町、旧日影町(春日町)の
区域が祭礼区域です。結構広い区域となっています。今回は、神社関係の提灯が主体です。
錦山神社参道の提灯 錦山神社入り口と階段のところです。文字は「錦山神社」
神社拝殿前の提灯。金森家の「梅鉢紋」となっています。
これについては、金森家二代可重が、慶長年間に錦山神社に稲荷社を勧請し、飛騨の
稲荷社の惣社としたことに由来しています。
錦町への入り口のところの提灯。
錦町と宗猷寺町の境目、酒屋さんのところの提灯。
この場所は、江名子町がここまできているために、複雑な場所が境目となっています。
(塩谷酒店のところは宗猷寺町。その横は江名子町となっています。)
錦町入り口、山本家裏の道の所です。
なぜか、無記名の提灯となっています。場所的にここに提灯があるのは不自然です。
錦山神社参道下の提灯。
江名子との境目に提灯があります。この提灯より神社側は錦町の新興住宅地域です。
かつて、私の小学校の時は、このあたりは田んぼでした。
宗猷寺町入り口の提灯。「御神燈」です。
基本的にこの場所は、愛宕神明神社との境になるはずなのですが、このような提灯になっており、
宗猷寺町と錦町の境目に神社の幟が揚げられています。不思議です。
このように、宗猷寺町の一番奥の所に幟があります。
これは、祭礼区域が昔と異なったのでしょうか。非常に謎です。
春日町入り口の幟旗。
実際には、現在の春日町の区域はもっと広く、ここから大隆寺側の山手にかけても春日町です。
これは、昭和16年の字と町名改正のときに、春日町に入れられた「日影町」という区域です。
護国神社下、島川原町と堀端町の境目の幟旗。お堀の東側。
ここに境目をあらわす幟があるのも不自然で、実際には、馬場町と堀端町の境目にあるべきです。
しかし、場所の関係で、この場所に設置されているものなのでしょう。
錦山神社の北側に鎮座される、錦山稲荷社の提灯。
春日町の秋葉様。提灯に神様の名前があります。
堀端町の秋葉様。こちらの提灯も独特のものです。
なお、島川原町秋葉様、宗猷寺町秋葉様については、撮り忘れました。
徳積善太
愛宕神明神社の提灯アラカルト
こちらも祭は終わってしまいましたが、愛宕神明神社(5月5日例祭)の提灯アラカルトです。
祭礼区域、愛宕町、天性寺町、吹屋町1丁目・2丁目

愛宕町一丁目の提灯(大雄寺下)
こちらの提灯は、文字は「献燈」ですが、微妙に提灯が異なります。



地元の人に伺ったら、地元の人も違いについてはご存じなくて、一緒だと思っておられました。
いつもたのむ提灯やさんに、どこの町内とつたえると大体造ってくださるそうですが、永年の
間に、少しづつ異なってきたのではとのことでした。
各家ごとに管理されているようです。

また、この通りは、昔は欠ノ上町という地域でしたが、通りの右側と左側で提灯が違う珍しい通りです。
これは、大雄寺に向って左側が若達町で、白山神社の氏子。右側が愛宕神明神社の氏子となって
いるために、こういうことが起こります。高山でもこういうのは、大変珍しいです。

同じ愛宕町でも、上の方へ行くと、提灯が異なります。これは「燈」です。

愛宕坂を上ると、東山町との境目にのぼりが有ります。現在は、国道端にありますが、元は
この道路はなく、もう少し右の旧道が平湯街道の出口でした。


この界隈は、行列も出ますが、子供神輿が各町内ごとにあります。この日も、愛宕町、天性寺町の
子供神輿に遭遇しました。ただし、吹屋町の子供神輿は、子供が少なくなり、神輿だけが寂しく
展示されていました。

吹屋町一丁目の提灯。愛宕坂上と同じ「燈」の提灯です。



吹屋町2丁目が大変面白く、場所によって提灯が異なります。おそらく班ごとに違うものと思われます。
この理由について、堀端町も同じだったので、錦山神社の人に聞いてわかったのですが、昔はこの地域は
火消し組みの、「愛宕組」と「東組」の地域だった。それで、現在の消防組が、○分団の第△班というように
分かれていたため、神社の祭礼でも、集団意識が分かれていた。そのため、班によって提灯が異なるように
なっていたとのことでした。これは大発見でした。地元の人も殆んど知らない事だと思います。
ちなみに、吹屋町2丁目の本通りの提灯には、「歓仰徳」(かんぎょうとく)と書かれています。
神様の徳にすがりつく想いを示したものでしょうか。神様の徳を仰ぎ見る事を喜ぶという意味だと思います。
大変珍しい提灯です。


天性寺町の提灯です。

吹屋町2丁目の秋葉様 提灯やのぼりをたてて化粧をしています。



こちらは、祭りの区域内にある素玄寺。 金森公の菩提寺らしく、金森公の梅鉢紋の提灯となっています。
また、本堂にも幕が掲げられて、化粧をされています。神様の祭りなのに、どうして仏閣がお祭りを迎えて
正装するのか、大変面白い事実だと思いました。
それは、このような理由からのようです。
かつてこの東山には、霊雲寺が古刹としてあり、白山神社を鎮守の神様としてお祭りしていました。
大雄寺ご住職によると、堀安信(ほりあんじん、ほりやすのぶ)という人が、京都から薬師として長近についてきて、
高山城の城下町の設計を行った。その褒美に何かないかたずねられたとき、彼は、法然上人の信者だったので、
願わくは浄土宗のお寺をこの高山の城下に移して欲しいと城主に頼んだそうです。
そのとき、浄土宗のお寺は、大雄寺が国府町の上広瀬に唯一ありました。
そこで、長近は、東山一帯を大雄寺に寄進しました。この愛宕神明神社自体が、大雄寺の鎮守の神様だったらしく、
その別当として天照寺が造られました。天照寺は、国府の名張にありましたが、天台宗の古刹でしたが、荒廃が
はげしく、浄土宗に転宗して、愛宕神社の守りをすることになりました。
少し後に東山へ、法華寺が西之一色から移転。次に金森の菩提寺として素玄寺が建てられ、その寺坊として
善応寺が松倉下の城下町から移転されて来ました。また、宗猷寺は、新安国寺として建てられました。
国道ができ、道が拡幅されることになって、善応寺が現在地に移転されたそうです。
徳積善太
祭礼区域、愛宕町、天性寺町、吹屋町1丁目・2丁目
愛宕町一丁目の提灯(大雄寺下)
こちらの提灯は、文字は「献燈」ですが、微妙に提灯が異なります。
地元の人に伺ったら、地元の人も違いについてはご存じなくて、一緒だと思っておられました。
いつもたのむ提灯やさんに、どこの町内とつたえると大体造ってくださるそうですが、永年の
間に、少しづつ異なってきたのではとのことでした。
各家ごとに管理されているようです。
また、この通りは、昔は欠ノ上町という地域でしたが、通りの右側と左側で提灯が違う珍しい通りです。
これは、大雄寺に向って左側が若達町で、白山神社の氏子。右側が愛宕神明神社の氏子となって
いるために、こういうことが起こります。高山でもこういうのは、大変珍しいです。
同じ愛宕町でも、上の方へ行くと、提灯が異なります。これは「燈」です。
愛宕坂を上ると、東山町との境目にのぼりが有ります。現在は、国道端にありますが、元は
この道路はなく、もう少し右の旧道が平湯街道の出口でした。
この界隈は、行列も出ますが、子供神輿が各町内ごとにあります。この日も、愛宕町、天性寺町の
子供神輿に遭遇しました。ただし、吹屋町の子供神輿は、子供が少なくなり、神輿だけが寂しく
展示されていました。
吹屋町一丁目の提灯。愛宕坂上と同じ「燈」の提灯です。
吹屋町2丁目が大変面白く、場所によって提灯が異なります。おそらく班ごとに違うものと思われます。
この理由について、堀端町も同じだったので、錦山神社の人に聞いてわかったのですが、昔はこの地域は
火消し組みの、「愛宕組」と「東組」の地域だった。それで、現在の消防組が、○分団の第△班というように
分かれていたため、神社の祭礼でも、集団意識が分かれていた。そのため、班によって提灯が異なるように
なっていたとのことでした。これは大発見でした。地元の人も殆んど知らない事だと思います。
ちなみに、吹屋町2丁目の本通りの提灯には、「歓仰徳」(かんぎょうとく)と書かれています。
神様の徳にすがりつく想いを示したものでしょうか。神様の徳を仰ぎ見る事を喜ぶという意味だと思います。
大変珍しい提灯です。
天性寺町の提灯です。
吹屋町2丁目の秋葉様 提灯やのぼりをたてて化粧をしています。
こちらは、祭りの区域内にある素玄寺。 金森公の菩提寺らしく、金森公の梅鉢紋の提灯となっています。
また、本堂にも幕が掲げられて、化粧をされています。神様の祭りなのに、どうして仏閣がお祭りを迎えて
正装するのか、大変面白い事実だと思いました。
それは、このような理由からのようです。
かつてこの東山には、霊雲寺が古刹としてあり、白山神社を鎮守の神様としてお祭りしていました。
大雄寺ご住職によると、堀安信(ほりあんじん、ほりやすのぶ)という人が、京都から薬師として長近についてきて、
高山城の城下町の設計を行った。その褒美に何かないかたずねられたとき、彼は、法然上人の信者だったので、
願わくは浄土宗のお寺をこの高山の城下に移して欲しいと城主に頼んだそうです。
そのとき、浄土宗のお寺は、大雄寺が国府町の上広瀬に唯一ありました。
そこで、長近は、東山一帯を大雄寺に寄進しました。この愛宕神明神社自体が、大雄寺の鎮守の神様だったらしく、
その別当として天照寺が造られました。天照寺は、国府の名張にありましたが、天台宗の古刹でしたが、荒廃が
はげしく、浄土宗に転宗して、愛宕神社の守りをすることになりました。
少し後に東山へ、法華寺が西之一色から移転。次に金森の菩提寺として素玄寺が建てられ、その寺坊として
善応寺が松倉下の城下町から移転されて来ました。また、宗猷寺は、新安国寺として建てられました。
国道ができ、道が拡幅されることになって、善応寺が現在地に移転されたそうです。
徳積善太
東山白山神社の提灯アラカルト
祭は終わってしまいましたが、東山白山神社の提灯についてお知らせします。
この地域は、若達町1丁目・2丁目。鉄砲町。大門町の4つの町内が祭礼区域となっています。
祭礼区域が小さいせいか、各町内ごとに提灯が分かれることなく、どれも同じ提灯になっています。

若達町の提灯 白山神社の社紋になっています。

大門町の提灯 白山神社の社紋になっています。

鉄砲町の提灯 白山神社の社紋になっています。

お旅所の提灯 白山神社の社紋の提灯がたくさんあります。
<秋葉様編>


若達町1丁目秋葉様 明威暉(めいかくき)と読むのでしょうか。
意味は、「神様の光があまねく輝き照らす」という意味だと思います。

若達町2丁目秋葉様 こちらには提灯がありませんでした。

鉄砲町秋葉様 こちらにも提灯はありませんでした。

東山白山神社神楽台 屋台蔵 提灯 シンプルに「御神燈」(ごしんとう)です。


東山白山神社 参道 提灯 「暉昱」(キイク) だと思いますが、輝きがあきらかであることをいうのだと
思います。昱(イク)は、あきらかの意。

大門町入り口の提灯 「白山大神」となっています。


最後に、大門町の秋葉様の提灯です。
徳積善太
この地域は、若達町1丁目・2丁目。鉄砲町。大門町の4つの町内が祭礼区域となっています。
祭礼区域が小さいせいか、各町内ごとに提灯が分かれることなく、どれも同じ提灯になっています。
若達町の提灯 白山神社の社紋になっています。
大門町の提灯 白山神社の社紋になっています。
鉄砲町の提灯 白山神社の社紋になっています。
お旅所の提灯 白山神社の社紋の提灯がたくさんあります。
<秋葉様編>
若達町1丁目秋葉様 明威暉(めいかくき)と読むのでしょうか。
意味は、「神様の光があまねく輝き照らす」という意味だと思います。
若達町2丁目秋葉様 こちらには提灯がありませんでした。
鉄砲町秋葉様 こちらにも提灯はありませんでした。
東山白山神社神楽台 屋台蔵 提灯 シンプルに「御神燈」(ごしんとう)です。
東山白山神社 参道 提灯 「暉昱」(キイク) だと思いますが、輝きがあきらかであることをいうのだと
思います。昱(イク)は、あきらかの意。
大門町入り口の提灯 「白山大神」となっています。
最後に、大門町の秋葉様の提灯です。
徳積善太
提燈アラカルト(飛騨総社編)
今日は、飛騨総社のお祭りの提燈について、お知らせします。

本町四丁目の提燈 「敬蜀」(ケイショク) 蝋燭の明かりを敬うという意味だそうです。

同じく、本町四丁目の提燈 こちらは「本燭」 でしょうか。 同じ町内でしかも隣同士なのに
提燈の種類が異なります。

こちらは、七日町一丁目の提燈 「榮煌」(ケイコウ)
「榮」は、1.①ひかり。ともしびの光。②ひかる。ひかりかがやく。③ひかりの少しくあらわれるさま。
④光のゆれて定まらぬさま。⑤あきらか。⑥ともしび。小さい光のともしび。⑦まどう。まどはす。
くらむ。目がちらつく。⑧ゑみ草。薬草の名。⑨ほたる。螢。⑩いとなむ。営に通ず。2.火の光。
等の意味があります。
また、「煌」は、1.①かがやく、かがやき。②さかん。盛。③日の菅田。④物のさま。2.かがやく。
3.火の光。4.あきらか。 という意味の漢字です。
[熒煌]ケイコウというのは、 ひかりかがやく。という意味で、白居易の漢文に使われています。
「赫奕冠蓋盛、熒煌朱紫爛」

こちらの提燈には、個人名が後ろに書かれています。これは意味があるのかと思ったら、
この地域では、各個人で提燈を調達しているからだとのこと。


そのため、同じ町内で隣同士なのに、提燈が異なるところが、こちらにもありました。
この提燈は、「敬熀」(ケイコウ) あきらかな光を敬うという意味です。
読みは同じですね。

 自家の家紋が入っているものもあります。
自家の家紋が入っているものもあります。
この点について、桐谷先生が同じ町内ですので、お尋ねしたら、
「第二次大戦後、此の町内にはあまり家がなかった。最初は、ところどころしか家がなくて、提燈も
ばらばらだった。昭和40年代に一度、お金を出し合って、提燈を一斉に作り変えた事があったが、
その後、提燈が破れたりした場合、個人の責任で修繕することになっていた。
そのため、各個人で気に入ったものを作るようになったために、違う提燈が存在する事になった。
春祭り、秋祭りの氏子のように統一したものがないので、このような事態になったんです。
また、傘の色、総の色も統一性がないから、見てみるといいよ。」
というお答えをいただきました。
私達、春祭りの氏子では、考えられない事ですが、これも高山の文化だと思いました。
さて、外の地域の提燈。

七日町三丁目から、桐生町にかけての提燈。
「献燈」です。 これは、比較的オーソドックスなタイプ。
ただし、結構広範囲にわたって、此の提燈が見られます。
この理由は、この地域が、昔、白山神社の氏子の区域だった事によるものと思われます。
現在は、飛騨総社の方へ合祀されましたが、現在のお旅所になっているところ(総和町地内)
に白山神社がありました。

こちらは、神田町1丁目の提燈。
「燈」(トウ)ですね。ろうそくのともし火=神様の光 という意味です。


神田町2丁目の提燈。
「敬熀」(ケイコウ) あきらかな光を敬うという意味です。逆光で撮ったら、光の線ができました。
神様の光が差したのでしょうか?

初田町1・2丁目の提燈。
こちらも「敬熀」(ケイコウ)です。

花岡町1・2丁目の提燈。
こちらも「敬熀」(ケイコウ)です。結構、広範囲にこの提燈がありますね。


線路を渡ると、富士神社との境目になっていました。

こちらは、昭和町3丁目の提燈。 浄土真宗大谷派と同じ上り藤になっています。
これは、どうしてこの提燈なのでしょうか?これは疑問です。
ひょっとすると、これは、富士神社の提燈かもしれません。未確認です。


昭和町1・2丁目の提燈。 こちらは、「熀」(コウ)で、丸提燈です。

昭和町のところは、2丁目と3丁目のところで、境目になっています。


本町3丁目は、「燈」が主流ですが、中には、「熀」(コウ)というのもありました。どちらも丸提燈です。


ところで、こんな違いも見つけました。横に書いてあるのが、一つは「総社」。もう一つは「懸社」と
なっています。どちらも飛騨総社のことですが、「懸社」と書いてあるほうが古いもののようです。
昔は、飛騨総社のことを「懸社(けんしゃ)」と呼んでいましたが、今では「総社(そうじゃ)」の方が
一般的なのでしょうね。
徳積善太
本町四丁目の提燈 「敬蜀」(ケイショク) 蝋燭の明かりを敬うという意味だそうです。
同じく、本町四丁目の提燈 こちらは「本燭」 でしょうか。 同じ町内でしかも隣同士なのに
提燈の種類が異なります。
こちらは、七日町一丁目の提燈 「榮煌」(ケイコウ)
「榮」は、1.①ひかり。ともしびの光。②ひかる。ひかりかがやく。③ひかりの少しくあらわれるさま。
④光のゆれて定まらぬさま。⑤あきらか。⑥ともしび。小さい光のともしび。⑦まどう。まどはす。
くらむ。目がちらつく。⑧ゑみ草。薬草の名。⑨ほたる。螢。⑩いとなむ。営に通ず。2.火の光。
等の意味があります。
また、「煌」は、1.①かがやく、かがやき。②さかん。盛。③日の菅田。④物のさま。2.かがやく。
3.火の光。4.あきらか。 という意味の漢字です。
[熒煌]ケイコウというのは、 ひかりかがやく。という意味で、白居易の漢文に使われています。
「赫奕冠蓋盛、熒煌朱紫爛」
こちらの提燈には、個人名が後ろに書かれています。これは意味があるのかと思ったら、
この地域では、各個人で提燈を調達しているからだとのこと。
そのため、同じ町内で隣同士なのに、提燈が異なるところが、こちらにもありました。
この提燈は、「敬熀」(ケイコウ) あきらかな光を敬うという意味です。
読みは同じですね。
この点について、桐谷先生が同じ町内ですので、お尋ねしたら、
「第二次大戦後、此の町内にはあまり家がなかった。最初は、ところどころしか家がなくて、提燈も
ばらばらだった。昭和40年代に一度、お金を出し合って、提燈を一斉に作り変えた事があったが、
その後、提燈が破れたりした場合、個人の責任で修繕することになっていた。
そのため、各個人で気に入ったものを作るようになったために、違う提燈が存在する事になった。
春祭り、秋祭りの氏子のように統一したものがないので、このような事態になったんです。
また、傘の色、総の色も統一性がないから、見てみるといいよ。」
というお答えをいただきました。
私達、春祭りの氏子では、考えられない事ですが、これも高山の文化だと思いました。
さて、外の地域の提燈。
七日町三丁目から、桐生町にかけての提燈。
「献燈」です。 これは、比較的オーソドックスなタイプ。
ただし、結構広範囲にわたって、此の提燈が見られます。
この理由は、この地域が、昔、白山神社の氏子の区域だった事によるものと思われます。
現在は、飛騨総社の方へ合祀されましたが、現在のお旅所になっているところ(総和町地内)
に白山神社がありました。
こちらは、神田町1丁目の提燈。
「燈」(トウ)ですね。ろうそくのともし火=神様の光 という意味です。
神田町2丁目の提燈。
「敬熀」(ケイコウ) あきらかな光を敬うという意味です。逆光で撮ったら、光の線ができました。
神様の光が差したのでしょうか?
初田町1・2丁目の提燈。
こちらも「敬熀」(ケイコウ)です。
花岡町1・2丁目の提燈。
こちらも「敬熀」(ケイコウ)です。結構、広範囲にこの提燈がありますね。
線路を渡ると、富士神社との境目になっていました。
こちらは、昭和町3丁目の提燈。 浄土真宗大谷派と同じ上り藤になっています。
これは、どうしてこの提燈なのでしょうか?これは疑問です。
ひょっとすると、これは、富士神社の提燈かもしれません。未確認です。
昭和町1・2丁目の提燈。 こちらは、「熀」(コウ)で、丸提燈です。
昭和町のところは、2丁目と3丁目のところで、境目になっています。
本町3丁目は、「燈」が主流ですが、中には、「熀」(コウ)というのもありました。どちらも丸提燈です。
ところで、こんな違いも見つけました。横に書いてあるのが、一つは「総社」。もう一つは「懸社」と
なっています。どちらも飛騨総社のことですが、「懸社」と書いてあるほうが古いもののようです。
昔は、飛騨総社のことを「懸社(けんしゃ)」と呼んでいましたが、今では「総社(そうじゃ)」の方が
一般的なのでしょうね。
徳積善太
古川まつりの提燈アラカルト1
今週末には、古川まつりが開催されます。
今日は、古川祭りのちょうちんについて、ご案内いたします。

上町地区の提燈。「奉照」というのは、照らし奉ると読むのでしょうか。ここは、正確には、
貴船神社の区域になります。


向町 神楽台の提燈。「神」には、足をつけて、図案化し、もう一つは、白が上に出ていますが、
「楽」の字を図案化したものと思われます。いわゆる遊びの精神でしょうか。

神楽台組(向町)1 この地区は、2種類の提燈がある珍しい屋台組です。
最初のものは、「献燈」です。

神楽台組(向町)2 2つ目の提燈は、「美四月」と書きますが、おそらく「美明」のことで、
「みあかし」と読ませるのだと思います。これは、「神様の光」という意味です。
しかし、どうして「日」の代わりに「四」なのか。「美しい四月」これも文字の遊びだと思われます。

三番叟組(壱之町上組)の提燈。 「献燈」です。明かりを献上するという意味でしょう。

鳳凰台組(壱之町中組)の提燈。こちらは「献鐙」です。献燈の意味だと思いますが、
金へんの「鐙」というのは、実際には「あぶみ」と読みます。馬の馬具のことです。
屋台の名称と絵が横に書かれています。

青龍台組(殿町)の提燈。こちらも「献鐙」です。殿町は、昔、馬場のあったところで、
馬の練習がされていたために、「あぶみ」の文字を使ったのでしょうか。

三光台組(弐之町上)の当番会所の提燈。


金亀台組(弐之町中)の当番会所と、街中の提燈。
会所の提燈は、「御神燈」だが、街中のものは、「奉燈」となっている。

龍笛台(弐之町下)の提燈。こちらも「献燈」の文字。龍の絵と龍笛台の文字。


清耀台組(三之町上)の提燈。

闘鶏楽組(栄町)の提燈。横に、闘鶏楽の文字。こちらも金へんになっていて、「あぶみ」の文字。
麒麟台組(壱之町下)の提燈と白虎台組(三之町下)・三光台(弐之町上)は、撮影していないことがわかりました。
今年の祭りで、撮りたいと思います。次回は、辻の提燈をご紹介します。
徳積善太
今日は、古川祭りのちょうちんについて、ご案内いたします。
上町地区の提燈。「奉照」というのは、照らし奉ると読むのでしょうか。ここは、正確には、
貴船神社の区域になります。
向町 神楽台の提燈。「神」には、足をつけて、図案化し、もう一つは、白が上に出ていますが、
「楽」の字を図案化したものと思われます。いわゆる遊びの精神でしょうか。
神楽台組(向町)1 この地区は、2種類の提燈がある珍しい屋台組です。
最初のものは、「献燈」です。
神楽台組(向町)2 2つ目の提燈は、「美四月」と書きますが、おそらく「美明」のことで、
「みあかし」と読ませるのだと思います。これは、「神様の光」という意味です。
しかし、どうして「日」の代わりに「四」なのか。「美しい四月」これも文字の遊びだと思われます。
三番叟組(壱之町上組)の提燈。 「献燈」です。明かりを献上するという意味でしょう。
鳳凰台組(壱之町中組)の提燈。こちらは「献鐙」です。献燈の意味だと思いますが、
金へんの「鐙」というのは、実際には「あぶみ」と読みます。馬の馬具のことです。
屋台の名称と絵が横に書かれています。
青龍台組(殿町)の提燈。こちらも「献鐙」です。殿町は、昔、馬場のあったところで、
馬の練習がされていたために、「あぶみ」の文字を使ったのでしょうか。
三光台組(弐之町上)の当番会所の提燈。
金亀台組(弐之町中)の当番会所と、街中の提燈。
会所の提燈は、「御神燈」だが、街中のものは、「奉燈」となっている。
龍笛台(弐之町下)の提燈。こちらも「献燈」の文字。龍の絵と龍笛台の文字。
清耀台組(三之町上)の提燈。
闘鶏楽組(栄町)の提燈。横に、闘鶏楽の文字。こちらも金へんになっていて、「あぶみ」の文字。
麒麟台組(壱之町下)の提燈と白虎台組(三之町下)・三光台(弐之町上)は、撮影していないことがわかりました。
今年の祭りで、撮りたいと思います。次回は、辻の提燈をご紹介します。
徳積善太
今日の高山祭1 提灯アラカルトその2
先日、提灯について、お知らせしましたが、今日、不足分を撮影しましたのでお知らせします。

西町 陵王台組の提灯 「煌栄」(こうえい) こうごうしい光が輝き栄えると言う意味。

陣屋前の通りを一歩西町に入ったところの境目の提灯。「祥輝厳照」(しょうきげんしょう)と
読むのでしょうか。意味については、わかりません。

陣屋前の本町一丁目側のところは、日枝神社の区域となっており、この提灯があります。
「清輝丹如」(せいきたんにょ)でしょうか。これも意味が解りません。

本町一丁目の裏通りは、慶祥組といって、神輿組です。ここは「神焔」(神ほのお)の文字です。

裏通りから本局通りに出たところは、有楽町といいますが、昔は裏町(浦町)といいました。
有楽組は神輿組です。

ここの、南側3軒だけは、提灯が異なります。「厳 火希」(げんき)と読むのでしょうか。
組みも提灯の意味も不明です。
この場所では、行列が一つの通りの右側を信号手前まで行って、左側を引き返す、
不思議な行列の運行がなされます。

この先は、天満神社区域、一本杉白山神社区域が交錯する場所です。
2つの神社の提灯が遠くに見えます。


有楽組の提灯 「焔(ほのお)」です。勾玉がついたタイプとついていないのとあります。

一瞬、有楽町から出たところが、一本杉白山神社の区域になっています。

本町2から、さんまち通りを通り、えび坂を上がると素晴らしい景色が見れます。

橘組(神輿組)の提灯。 麒麟臺から分派したために、同じ提灯となっています。

行列は、安川へでて、文右衛門坂を下り、上二之町を上がり、上三之町に入ります。
写真は、敬祥組の提灯。この組は、NTTができて組員が減りましたが、かつては12軒の組でした。
石橋台にも南車台にも所属せず、独立した組として神輿組を維持しました。

瓢箪組(ひょうたんくみ=上三之町下組)は、神輿組です。

私も知らなかったのですが、祭の時には、瓢箪組の由来の看板が出るようです。
そこには、こう書いてあります。
「不動(うごかず)の御旗
天保三年飛州上野の笹原に花開き実を結んでより打ち続く諸作不熟で飢饉その
域に達し餓死者疫死者相次ぎ野にも里にも死屍が横わった。
この凶荒を救ふには天の恵にたよるより外なしと考へ天保八年丁酉三月角屋伊兵衛組の
組頭が飛騨郡代大井帯刀の許を得て京都に入方としての世話人広瀬屋利兵衛、近藤屋
勘十郎、無雁屋嘉十郎を選び日月の御旗を発注せしめ豊臣秀吉公のゆかりの豊国神社に
祈願を込めるとともに社宝の瓢箪をもらって帰高し組名を瓢箪組と改め只管御旗の守護に
努め、日夜之を奉拝したる処郡代大井帯刀の検見寛大の取計と相なって庶民は生気を
取り戻した。示来あらたかな御旗の霊験を仕て得た庶民は災難よけとして信仰一入厚い
ものとなった。 瓢箪組」

そこには、秋葉様のようなお社があって、この提灯が掲げてある。「迦皇出神」と読むのか。
この意味は、不明である。

片原町の出口、交番の処の提灯。この鳩らしき模様は、以前気づかなかったが、どうして
この鳩マークなのかは不明。屋台組の文様とも異なる。

先日もお知らせした、「三安佳四」(みあかし=神様の光)。当て字となっている。
崑崗台組の提灯。

この日は、どこの秋葉様も、きれいにやわってもらって、提灯と御旗が掲げられている。
<番外編>

これは、隣の祭礼区域。一本杉白山神社の提灯です。「清照」(せいしょう)。
読んで字の如し「清らかに照らす」と言う意味です。
高山陣屋は、一本杉白山神社の区域ですが、西町から八軒町にかけては、日枝神社の区域と
一本杉白山神社の区域が混合しています。昔、行列を陣屋に立ち寄らせるために、陣屋前通り
を通ったのでしょうか、毎年、この場所を通る習わしになっています。

ところが、一本杉白山神社の行列がいつも同じ時間にこの場所を通るために、けんかが絶えません
でした。わざとこの時間にしていたことがあったらしいですが、どちらが先に通るか、もめたそうです。
今では、紳士的に、日枝神社が通るときには、一本杉の行列を先に通す慣わしになっています。

一旦、一本杉の行列の行過ぎるのを待つ日枝神社行列(本教寺前、西町通りにて)
徳積善太
西町 陵王台組の提灯 「煌栄」(こうえい) こうごうしい光が輝き栄えると言う意味。
陣屋前の通りを一歩西町に入ったところの境目の提灯。「祥輝厳照」(しょうきげんしょう)と
読むのでしょうか。意味については、わかりません。
陣屋前の本町一丁目側のところは、日枝神社の区域となっており、この提灯があります。
「清輝丹如」(せいきたんにょ)でしょうか。これも意味が解りません。
本町一丁目の裏通りは、慶祥組といって、神輿組です。ここは「神焔」(神ほのお)の文字です。
裏通りから本局通りに出たところは、有楽町といいますが、昔は裏町(浦町)といいました。
有楽組は神輿組です。
ここの、南側3軒だけは、提灯が異なります。「厳 火希」(げんき)と読むのでしょうか。
組みも提灯の意味も不明です。
この場所では、行列が一つの通りの右側を信号手前まで行って、左側を引き返す、
不思議な行列の運行がなされます。
この先は、天満神社区域、一本杉白山神社区域が交錯する場所です。
2つの神社の提灯が遠くに見えます。
有楽組の提灯 「焔(ほのお)」です。勾玉がついたタイプとついていないのとあります。
一瞬、有楽町から出たところが、一本杉白山神社の区域になっています。
本町2から、さんまち通りを通り、えび坂を上がると素晴らしい景色が見れます。
橘組(神輿組)の提灯。 麒麟臺から分派したために、同じ提灯となっています。
行列は、安川へでて、文右衛門坂を下り、上二之町を上がり、上三之町に入ります。
写真は、敬祥組の提灯。この組は、NTTができて組員が減りましたが、かつては12軒の組でした。
石橋台にも南車台にも所属せず、独立した組として神輿組を維持しました。
瓢箪組(ひょうたんくみ=上三之町下組)は、神輿組です。
私も知らなかったのですが、祭の時には、瓢箪組の由来の看板が出るようです。
そこには、こう書いてあります。
「不動(うごかず)の御旗
天保三年飛州上野の笹原に花開き実を結んでより打ち続く諸作不熟で飢饉その
域に達し餓死者疫死者相次ぎ野にも里にも死屍が横わった。
この凶荒を救ふには天の恵にたよるより外なしと考へ天保八年丁酉三月角屋伊兵衛組の
組頭が飛騨郡代大井帯刀の許を得て京都に入方としての世話人広瀬屋利兵衛、近藤屋
勘十郎、無雁屋嘉十郎を選び日月の御旗を発注せしめ豊臣秀吉公のゆかりの豊国神社に
祈願を込めるとともに社宝の瓢箪をもらって帰高し組名を瓢箪組と改め只管御旗の守護に
努め、日夜之を奉拝したる処郡代大井帯刀の検見寛大の取計と相なって庶民は生気を
取り戻した。示来あらたかな御旗の霊験を仕て得た庶民は災難よけとして信仰一入厚い
ものとなった。 瓢箪組」
そこには、秋葉様のようなお社があって、この提灯が掲げてある。「迦皇出神」と読むのか。
この意味は、不明である。
片原町の出口、交番の処の提灯。この鳩らしき模様は、以前気づかなかったが、どうして
この鳩マークなのかは不明。屋台組の文様とも異なる。
先日もお知らせした、「三安佳四」(みあかし=神様の光)。当て字となっている。
崑崗台組の提灯。
この日は、どこの秋葉様も、きれいにやわってもらって、提灯と御旗が掲げられている。
<番外編>
これは、隣の祭礼区域。一本杉白山神社の提灯です。「清照」(せいしょう)。
読んで字の如し「清らかに照らす」と言う意味です。
高山陣屋は、一本杉白山神社の区域ですが、西町から八軒町にかけては、日枝神社の区域と
一本杉白山神社の区域が混合しています。昔、行列を陣屋に立ち寄らせるために、陣屋前通り
を通ったのでしょうか、毎年、この場所を通る習わしになっています。
ところが、一本杉白山神社の行列がいつも同じ時間にこの場所を通るために、けんかが絶えません
でした。わざとこの時間にしていたことがあったらしいですが、どちらが先に通るか、もめたそうです。
今では、紳士的に、日枝神社が通るときには、一本杉の行列を先に通す慣わしになっています。
一旦、一本杉の行列の行過ぎるのを待つ日枝神社行列(本教寺前、西町通りにて)
徳積善太
高山祭の提燈
高山祭の氏子区域になる場所には、境目のところに提燈が掲げられます。
そのいくつかをご紹介しましょう。

上一之町入り口のもの
「美明火」=みあかしと読みます。神様の火(光)という意味です。

上二之町入り口のもの
読んで字の如し。「飛騨山王宮」=日枝神社のことです。

上三之町入り口のもの
読んで字の如し、「飛騨日枝神社」の提燈です。

片原町入り口
読んで字の如し、「飛騨日枝社」です。

馬場町二丁目入り口のもの
上一と同じ、「美明火」=みあかしです。


馬場町入り口、えび坂上のもの
これがわからないんです。「かくいしょうてつ」とでも読むのでしょうか。
どなたに聞いてもご存じない方ばかりで、調べようがありません。どなたかご存知ですか?
不思議な事に、天満神社側、一本杉神社側については、日枝神社の境目の提燈はありません。
そちらの神社の提燈があります。

徳積善太
そのいくつかをご紹介しましょう。
上一之町入り口のもの
「美明火」=みあかしと読みます。神様の火(光)という意味です。
上二之町入り口のもの
読んで字の如し。「飛騨山王宮」=日枝神社のことです。
上三之町入り口のもの
読んで字の如し、「飛騨日枝神社」の提燈です。
片原町入り口
読んで字の如し、「飛騨日枝社」です。
馬場町二丁目入り口のもの
上一と同じ、「美明火」=みあかしです。
馬場町入り口、えび坂上のもの
これがわからないんです。「かくいしょうてつ」とでも読むのでしょうか。
どなたに聞いてもご存じない方ばかりで、調べようがありません。どなたかご存知ですか?
不思議な事に、天満神社側、一本杉神社側については、日枝神社の境目の提燈はありません。
そちらの神社の提燈があります。
徳積善太
高山祭の提燈アラカルト
高山祭の屋台のちょうちんなどについて、パンフレットで紹介された事がありますが、ブログに掲示します。

神楽台組の提燈(上一之町上組) 屋台の台紋 「楽」という字の図案化になっています。

三番叟組の提燈(上一之町中組) 屋台の台紋 恩雀台といった時期があり、「雀」の図案化となっています。

黄鶴台組の提燈(上一之町中組) 折鶴の形を図案化しています。「黄鶴」とは本来「オシドリ」のことを表しますが、「鶴」の文字を使っているので、「折り鶴」が使われているものと思われます。


麒麟台組の提燈。(上一之町下組) 台紋は、「麒麟の顔を正面から見たところ」の図案化です。提燈も同じです。

石橋台組の提燈(上二之町上組) 「日吉宮」というのは、日枝神社のこと。日が図案化されています。

南車台組の提燈(上二之町中組) 「ふくら雀」が使われています。理由は、福をもたらし、子孫繁栄を表すと言われています。


五台山組の提燈(上二之町中組) 台紋は、「獅子の正面図案化」です。提燈も同じです。

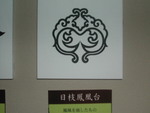
鳳凰台組の提燈。(上二之町下組) 台紋は、「鳳凰の正面図案化」です。提燈も同じです。

恵比須台組の提燈(上三之町上組) 現代文字にすると「献明燈」でしょうか。神様の光を献じるという意味です。

龍神台組の提燈(上三之町下組) 「龍の爪で玉を持っているという図」の図案化です。台紋も同じです。

崑崗台組の提燈(片原町) この「三安佳四」は、みあかしと読み、神様の光という意味です。当て字が使われています。

琴高台組の提燈(本町1) 「神が在るが如く」と書きますが「神、おわすが如く」と読むそうです。 常に神様の威光が降り注いでいる状態を示しているものと思われます。

応龍台組の提燈(本町2) 応龍とは、飛龍の事を言います。正面から見た飛龍の図案化したものです。台紋です。


提燈は琴高台と同じ「如神在」(神、おわすが如く) 台紋は、「打ち出の小槌」を三つ重ねたものです。この小槌は、大黒様の持ち物で、欲しいものが何でも出てくるという伝説のある小槌です。福を表します。

青龍台組の提燈 「徳輝遍」(とっきあまねく)とは、徳のある輝きがあまねく照らす=みあかし=神明 神様の光があまねく照らされる
という意味で、みあかしと同じ意味です。

陵王台の提燈。ここのは、 惶栄=(こうえい)神々しい光が栄え輝く という意味になっています。
その他 御輿組のものを一部撮っていますのでご紹介します。

橘組(馬場町2) 元麒麟台に属していたことから、同じ提燈になっています。 橘神社をお祭りしていましたが、老田酒造店の土地売却の後に日枝神社に合祀されました。

上神明組(神明町) 日枝神社のことを表わす「日吉宮」の文字。 石橋台神明組から独立したので、同じです。
「石橋台組」は、現在は「石橋台組」、「石橋台神明組」の2つがあり、同じ屋台組として活動していますがかつては屋台組と神輿組でした。
また、「弦上組」「上神明組」も「石橋台神明組」であったと思われますが、神輿組として独立した歴史があります。

野川そばさん。(神明町) 区域からすると「恵比須台組」なのですが、「三安組」と同じ提燈になっています。
野川さんの先代は、森下町にお住まいで、獅子組に所属され、神楽台の太鼓をたたいておられました。そのため、恵比須台組には所属せず、獅子組としての立場を明確にされていました。そのため、屋台組には所属されていないようです。

敬慎組(上二之町中) 元々この組は、長瀬屋弥兵衛(旧長瀬旅館)という家が中心で12戸ほどあった組ですが、南車台組にも石橋台
組にも属さない組として存在します。現NTTのところにたくさん家がありました。現在は、ブライダルのナガセ(旧長瀬旅館)の一軒だけの組となってしまい、神輿組としては存在しますが、活動はされていません。

森下組(神社入り口。森下町) 森下組は、もともと神輿組でしたが、昭和27年以降は「獅子組」を作り、「神楽台」に乗り、神楽組と協力しながら昭和28年以降、獅子舞の奉仕を行っています。(それまでは、江名子獅子が奉仕をされていました。)
森下組も片野組も同じ模様の丸提燈。画像とは違います。

城坂組(馬場町1丁目) この組は、明治24年に三番叟より独立して神輿組になったため、提燈は三番叟と同じです。
近年、神輿組も脱退され、宮本からは除外されています。

慶祥組(本町一丁目裏町) 天領時代からの御輿組。
このほかに、有楽組(有楽町)「組紋」、三安組(上三之町下)「焰」=かがり火、瓢箪組(上三之町下)「焰」=かがり火、
絃上組(神明町3丁目) 「和光」、片野組「日枝神社社紋」などがありますが、画像を撮っていません。
後日撮影しましたので別に掲載させていただきます。
徳積善太

神楽台組の提燈(上一之町上組) 屋台の台紋 「楽」という字の図案化になっています。
三番叟組の提燈(上一之町中組) 屋台の台紋 恩雀台といった時期があり、「雀」の図案化となっています。
黄鶴台組の提燈(上一之町中組) 折鶴の形を図案化しています。「黄鶴」とは本来「オシドリ」のことを表しますが、「鶴」の文字を使っているので、「折り鶴」が使われているものと思われます。

麒麟台組の提燈。(上一之町下組) 台紋は、「麒麟の顔を正面から見たところ」の図案化です。提燈も同じです。
石橋台組の提燈(上二之町上組) 「日吉宮」というのは、日枝神社のこと。日が図案化されています。
南車台組の提燈(上二之町中組) 「ふくら雀」が使われています。理由は、福をもたらし、子孫繁栄を表すと言われています。
五台山組の提燈(上二之町中組) 台紋は、「獅子の正面図案化」です。提燈も同じです。

鳳凰台組の提燈。(上二之町下組) 台紋は、「鳳凰の正面図案化」です。提燈も同じです。
恵比須台組の提燈(上三之町上組) 現代文字にすると「献明燈」でしょうか。神様の光を献じるという意味です。
龍神台組の提燈(上三之町下組) 「龍の爪で玉を持っているという図」の図案化です。台紋も同じです。
崑崗台組の提燈(片原町) この「三安佳四」は、みあかしと読み、神様の光という意味です。当て字が使われています。
琴高台組の提燈(本町1) 「神が在るが如く」と書きますが「神、おわすが如く」と読むそうです。 常に神様の威光が降り注いでいる状態を示しているものと思われます。
応龍台組の提燈(本町2) 応龍とは、飛龍の事を言います。正面から見た飛龍の図案化したものです。台紋です。

提燈は琴高台と同じ「如神在」(神、おわすが如く) 台紋は、「打ち出の小槌」を三つ重ねたものです。この小槌は、大黒様の持ち物で、欲しいものが何でも出てくるという伝説のある小槌です。福を表します。
青龍台組の提燈 「徳輝遍」(とっきあまねく)とは、徳のある輝きがあまねく照らす=みあかし=神明 神様の光があまねく照らされる
という意味で、みあかしと同じ意味です。
陵王台の提燈。ここのは、 惶栄=(こうえい)神々しい光が栄え輝く という意味になっています。
その他 御輿組のものを一部撮っていますのでご紹介します。
橘組(馬場町2) 元麒麟台に属していたことから、同じ提燈になっています。 橘神社をお祭りしていましたが、老田酒造店の土地売却の後に日枝神社に合祀されました。
上神明組(神明町) 日枝神社のことを表わす「日吉宮」の文字。 石橋台神明組から独立したので、同じです。
「石橋台組」は、現在は「石橋台組」、「石橋台神明組」の2つがあり、同じ屋台組として活動していますがかつては屋台組と神輿組でした。
また、「弦上組」「上神明組」も「石橋台神明組」であったと思われますが、神輿組として独立した歴史があります。
野川そばさん。(神明町) 区域からすると「恵比須台組」なのですが、「三安組」と同じ提燈になっています。
野川さんの先代は、森下町にお住まいで、獅子組に所属され、神楽台の太鼓をたたいておられました。そのため、恵比須台組には所属せず、獅子組としての立場を明確にされていました。そのため、屋台組には所属されていないようです。
敬慎組(上二之町中) 元々この組は、長瀬屋弥兵衛(旧長瀬旅館)という家が中心で12戸ほどあった組ですが、南車台組にも石橋台
組にも属さない組として存在します。現NTTのところにたくさん家がありました。現在は、ブライダルのナガセ(旧長瀬旅館)の一軒だけの組となってしまい、神輿組としては存在しますが、活動はされていません。
森下組(神社入り口。森下町) 森下組は、もともと神輿組でしたが、昭和27年以降は「獅子組」を作り、「神楽台」に乗り、神楽組と協力しながら昭和28年以降、獅子舞の奉仕を行っています。(それまでは、江名子獅子が奉仕をされていました。)
森下組も片野組も同じ模様の丸提燈。画像とは違います。
城坂組(馬場町1丁目) この組は、明治24年に三番叟より独立して神輿組になったため、提燈は三番叟と同じです。
近年、神輿組も脱退され、宮本からは除外されています。
慶祥組(本町一丁目裏町) 天領時代からの御輿組。
このほかに、有楽組(有楽町)「組紋」、三安組(上三之町下)「焰」=かがり火、瓢箪組(上三之町下)「焰」=かがり火、
絃上組(神明町3丁目) 「和光」、片野組「日枝神社社紋」などがありますが、画像を撮っていません。
後日撮影しましたので別に掲載させていただきます。
徳積善太