HOME › 飛騨の古城について
鍋山城に登ってきました
久しぶりの投稿です。
今日は、城郭研究家の先生の案内で鍋山城に初めて登ってきました。

知らなかったのですが、鍋山城は大鍋山=本丸、小鍋山=出丸、下鍋山=二之丸という3つの山に
分かれているんですね。
本丸の部分は結構広い場所で、ここにどんな館があったのか、歴史ロマンを語りました。

鍋山城の由緒について

本丸のところにある、鍋山城の碑。

上には立派な石垣があるのですが、大手から登った側にしか石垣はなく、これは急造した石垣で
あろうとのこと。
また、松倉城の石垣は、角のところが、大きな石→小さな石→大きな石と計画的に積まれているのに
対して、こちらのものは、まばらになっており、急造したことがわかるとのお話でした。
実は、このお城に住んでいた、三木自綱の弟 顕綱の命を狙ったのが、長瀬甚平と土川新左エ門という
2名です。書状にわざとわからない文字を書き入れており、その時にこれは何を書いてあるのだと尋ねた
殿様に、近くに行かないとわかりませんとのことで、おそば近くに立ち寄り、文字の説明を長瀬甚平が
していたところ、後ろから土川新左エ門が切りかかり、殿様の首を取ったそうです。
逃げるときに、半狂乱になった奥方が追いかけてきて、その首をはねたところ、大蛇になったという
伝説があります。これが、七夕岩の大綱の伝説として今に伝えられています。
この長瀬甚平は、我が家のご先祖様と伝わっています。
このところ、運動不足で、帰りには足がつってしまい、二之丸や出丸には行けませんでした。
体力作りが不可欠です。がんばります。
徳積善太
今日は、城郭研究家の先生の案内で鍋山城に初めて登ってきました。
知らなかったのですが、鍋山城は大鍋山=本丸、小鍋山=出丸、下鍋山=二之丸という3つの山に
分かれているんですね。
本丸の部分は結構広い場所で、ここにどんな館があったのか、歴史ロマンを語りました。
鍋山城の由緒について
本丸のところにある、鍋山城の碑。
上には立派な石垣があるのですが、大手から登った側にしか石垣はなく、これは急造した石垣で
あろうとのこと。
また、松倉城の石垣は、角のところが、大きな石→小さな石→大きな石と計画的に積まれているのに
対して、こちらのものは、まばらになっており、急造したことがわかるとのお話でした。
実は、このお城に住んでいた、三木自綱の弟 顕綱の命を狙ったのが、長瀬甚平と土川新左エ門という
2名です。書状にわざとわからない文字を書き入れており、その時にこれは何を書いてあるのだと尋ねた
殿様に、近くに行かないとわかりませんとのことで、おそば近くに立ち寄り、文字の説明を長瀬甚平が
していたところ、後ろから土川新左エ門が切りかかり、殿様の首を取ったそうです。
逃げるときに、半狂乱になった奥方が追いかけてきて、その首をはねたところ、大蛇になったという
伝説があります。これが、七夕岩の大綱の伝説として今に伝えられています。
この長瀬甚平は、我が家のご先祖様と伝わっています。
このところ、運動不足で、帰りには足がつってしまい、二之丸や出丸には行けませんでした。
体力作りが不可欠です。がんばります。
徳積善太
石光山に登ってきました
昨日、誘われて石光山に行ってきました。
石浦町の山の上で、以前から行ってみたいと思っておりましたが、ようやく念願がかないました。

ここは、『斐太後風土記』によると、平清輔朝臣と云う人が、鷹狩りの最中に霊現を感じ、日吉宮から勧請したといわれる場所です。
現在その神様は、高山祭りの春祭りで有名な日枝神社として、高山の町の人達に守られています。
江名子町の糠塚から車で途中まで行くと、そこからは石浦町の共有林になっており、鎖に鍵がかけられていました。
そこから、道なき道をヤブをかき分け、尾根を登っていくと、その場所はありました。

片野町の敬神会の皆さんが平成元年に建立された白い木柱と石浦町の方が建立された木柱が建てられていました。
その中央にはかつて社が有ったと思われる石積みがありましたが、すべて川石でできたものでした。
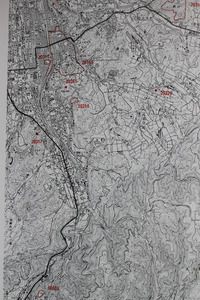

翌日、岐阜県山城悉皆調査の報告書を確認した所、全く違う場所が調査されて居ることが分かりました。
調査にあたられたのは、城郭研究家の佐伯先生ですが、それには、『高山市遺跡地図』を参考にしたとされていました。
その遺跡地図には、次のように書かれています。

「永治元年(1411)飛騨守平時輔が三仏寺城を築城した時、宮峠の峯に連なる片野と大西の境界山上に日吉宮を勧請し砦を築いて三仏寺城の守りとしたと伝えられる」
と記されています。また、参考文献は『飛騨の城』森本一雄著(昭和62年 郷土出版社)となっておりますので、その信ぴょう性は定かではありません。
早速、佐伯先生にこのことをご連絡し、6月位に一度案内する事になりました。
ながせきみあき
石浦町の山の上で、以前から行ってみたいと思っておりましたが、ようやく念願がかないました。

ここは、『斐太後風土記』によると、平清輔朝臣と云う人が、鷹狩りの最中に霊現を感じ、日吉宮から勧請したといわれる場所です。
現在その神様は、高山祭りの春祭りで有名な日枝神社として、高山の町の人達に守られています。
江名子町の糠塚から車で途中まで行くと、そこからは石浦町の共有林になっており、鎖に鍵がかけられていました。
そこから、道なき道をヤブをかき分け、尾根を登っていくと、その場所はありました。

片野町の敬神会の皆さんが平成元年に建立された白い木柱と石浦町の方が建立された木柱が建てられていました。
その中央にはかつて社が有ったと思われる石積みがありましたが、すべて川石でできたものでした。
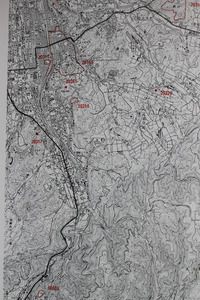

翌日、岐阜県山城悉皆調査の報告書を確認した所、全く違う場所が調査されて居ることが分かりました。
調査にあたられたのは、城郭研究家の佐伯先生ですが、それには、『高山市遺跡地図』を参考にしたとされていました。
その遺跡地図には、次のように書かれています。

「永治元年(1411)飛騨守平時輔が三仏寺城を築城した時、宮峠の峯に連なる片野と大西の境界山上に日吉宮を勧請し砦を築いて三仏寺城の守りとしたと伝えられる」
と記されています。また、参考文献は『飛騨の城』森本一雄著(昭和62年 郷土出版社)となっておりますので、その信ぴょう性は定かではありません。
早速、佐伯先生にこのことをご連絡し、6月位に一度案内する事になりました。
ながせきみあき
戦国の山城フォーラム3 基調講演
10分間休憩の後、中井均先生の講演を行ないました。

司会は私が勤めました。
中井先生のテーマは「飛騨の山城―その魅力を語るー」というお話をされました。

先生は、自分の言葉で、わかりやすく山城についてご説明くださいました。

岐阜県の中でも廣瀬城は、とてもきれいに残っている山城として、すごく魅力があるという
お話をくださいました。
中井先生の後、質疑応答があり、山下城についてなど質問がありました。
一旦、会を閉会し、副会長の下畑五夫さんが閉会のあいさつをされました。

そのあと、3先生に残っていただき、研究者のための質疑応答の会を持ちました。
突っ込んだ質問が結構ありましたが、議論に至るということはありませんでした。

一部、武田の飛騨侵攻に関する質問があり、私の専門でしたので、私から回答させていただきました。
お陰さまで無事、戦国の山城フォーラムを閉会する事ができました。
(つづく)
徳積善太

司会は私が勤めました。
中井先生のテーマは「飛騨の山城―その魅力を語るー」というお話をされました。

先生は、自分の言葉で、わかりやすく山城についてご説明くださいました。

岐阜県の中でも廣瀬城は、とてもきれいに残っている山城として、すごく魅力があるという
お話をくださいました。
中井先生の後、質疑応答があり、山下城についてなど質問がありました。
一旦、会を閉会し、副会長の下畑五夫さんが閉会のあいさつをされました。

そのあと、3先生に残っていただき、研究者のための質疑応答の会を持ちました。
突っ込んだ質問が結構ありましたが、議論に至るということはありませんでした。

一部、武田の飛騨侵攻に関する質問があり、私の専門でしたので、私から回答させていただきました。
お陰さまで無事、戦国の山城フォーラムを閉会する事ができました。
(つづく)
徳積善太
戦国の山城フォーラム2 研究発表
昼食を済ませてから1時半より城郭研究家の佐伯哲也先生と元高山市郷土館長 田中彰先生の研究
発表があり、そのあと基調講演として中井均先生の講演がありました。
実は、私が司会を務めさせていただきました。

まず佐伯哲也さんのお話がありました。
テーマは、佐伯先生が「飛騨の山城の時代的変遷」

飛騨地方には、100から154の山城があるとされていますが、研究者の見解によって数はわかれるとのこと。
富山が38万石に対して400の山城がありますが、飛騨地方には、38千石に対して150だとすると、非常に
密度が高いという話でした。

実際に、ご自身で作成された山城の図を提示しながらお話をされました。
続いて、田中彰先生によるお話がありました。
田中先生が「飛騨における武士団の集約と飛騨国統一」

飛騨地方にどんな武将がいたのか、具体的に名前をあげながらお話をされました。

また。江戸時代後期に書かれた絵地図で、飛騨の豪族がだれに支配されていたか、説明を
されました。

折角の機会ですので、質疑応答の時間を設けました。
なぜ、150もの山城が一挙にできたのか。それはどこの場所だったのかについて質問がありました。
それについては、古川盆地に一挙にできたとのことでしたが、そんな数があるのだろうかという疑問が
残りました。
会場の声がスピーカーの関係で、ステージ上では大変聞き取りにくく、質問内容がよくわからない状態
だったので、皆さんにご迷惑をおかけしました。
山城の数については、研究者の判断にゆだねられているところがあり、たとえば、寺洞城砦群などは、
4つの砦からできていますが、1と数えるか、4と数えるか。また、東砦・西砦などといったものを1と数えるか
2と数えるかで数が違ってきます。そういったことで、数を細かく数えると154という数になります。
(つづく)
徳積善太
発表があり、そのあと基調講演として中井均先生の講演がありました。
実は、私が司会を務めさせていただきました。

まず佐伯哲也さんのお話がありました。
テーマは、佐伯先生が「飛騨の山城の時代的変遷」

飛騨地方には、100から154の山城があるとされていますが、研究者の見解によって数はわかれるとのこと。
富山が38万石に対して400の山城がありますが、飛騨地方には、38千石に対して150だとすると、非常に
密度が高いという話でした。

実際に、ご自身で作成された山城の図を提示しながらお話をされました。
続いて、田中彰先生によるお話がありました。
田中先生が「飛騨における武士団の集約と飛騨国統一」

飛騨地方にどんな武将がいたのか、具体的に名前をあげながらお話をされました。

また。江戸時代後期に書かれた絵地図で、飛騨の豪族がだれに支配されていたか、説明を
されました。

折角の機会ですので、質疑応答の時間を設けました。
なぜ、150もの山城が一挙にできたのか。それはどこの場所だったのかについて質問がありました。
それについては、古川盆地に一挙にできたとのことでしたが、そんな数があるのだろうかという疑問が
残りました。
会場の声がスピーカーの関係で、ステージ上では大変聞き取りにくく、質問内容がよくわからない状態
だったので、皆さんにご迷惑をおかけしました。
山城の数については、研究者の判断にゆだねられているところがあり、たとえば、寺洞城砦群などは、
4つの砦からできていますが、1と数えるか、4と数えるか。また、東砦・西砦などといったものを1と数えるか
2と数えるかで数が違ってきます。そういったことで、数を細かく数えると154という数になります。
(つづく)
徳積善太
戦国の山城フォーラム1 廣瀬城登山
7月22日に国府町で歴史関係のイベント「戦国の山城フォーラム -国府の山城の謎に迫るー」が
行われました。
今日までいろいろと準備を重ねてまいりました。22日当日の方は、丸一日かけて三部構成で行われ
ますが、朝9時に国府支所前に集合して廣瀬城を全国の城郭研究家 中井均先生と一緒に登りました。
当日は、遠くは徳島県からや名古屋などから、県外より12名の皆さんを含む50名の皆さんがご参加
くださいました。

早い方は8時半頃には会場に来ていただいていました。

開会にあたり、今日のスケジュールを説明しました。

開会に先立ち、酒井会長のあいさつ。

皆さんがそれぞれ、バスに乗り込みます。
旧国府町役場→廣瀬城跡見学→国府支所へとバスは進みます。
だいたい、午前中かけてのミニツアーです。

最初、国府町役場のところに車を止め、廣瀬城と高堂城が見える場所へ行きました。
酒井先生の説明がありました。

続いて、廣瀬城にあがりました。
田中筑前守の墓碑のところで、酒井先生の説明を聞きました。

そこから、大堀切を上がり、廣瀬城に上りました。
ここからは、中井均先生の説明を聞きました。

本丸下の石垣のところの説明。小さな石積みが残っています。

中井先生の説明はわかりやすく、熱心に話を聞く参加者の皆さん。
大変わかりやすかったと、好評な会となりました。
(つづく)
徳積善太
行われました。
今日までいろいろと準備を重ねてまいりました。22日当日の方は、丸一日かけて三部構成で行われ
ますが、朝9時に国府支所前に集合して廣瀬城を全国の城郭研究家 中井均先生と一緒に登りました。
当日は、遠くは徳島県からや名古屋などから、県外より12名の皆さんを含む50名の皆さんがご参加
くださいました。
早い方は8時半頃には会場に来ていただいていました。

開会にあたり、今日のスケジュールを説明しました。

開会に先立ち、酒井会長のあいさつ。

皆さんがそれぞれ、バスに乗り込みます。
旧国府町役場→廣瀬城跡見学→国府支所へとバスは進みます。
だいたい、午前中かけてのミニツアーです。

最初、国府町役場のところに車を止め、廣瀬城と高堂城が見える場所へ行きました。
酒井先生の説明がありました。

続いて、廣瀬城にあがりました。
田中筑前守の墓碑のところで、酒井先生の説明を聞きました。

そこから、大堀切を上がり、廣瀬城に上りました。
ここからは、中井均先生の説明を聞きました。

本丸下の石垣のところの説明。小さな石積みが残っています。

中井先生の説明はわかりやすく、熱心に話を聞く参加者の皆さん。
大変わかりやすかったと、好評な会となりました。
(つづく)
徳積善太
戦国の山城フォーラム_パネル造り

(廣瀬城の畝状竪堀)
今日は、22日に行われる「戦国の山城フォーラム」のプレイベントとして開催する、パネル展示
のために、パネルの制作を行ないました。
国府町には28個の山城・砦・山岳寺院が確認されています。
1)廣瀬城跡 国府町名張~瓜巣 (県指定史跡)
2)高堂城跡 国府町瓜巣 (県指定史跡)
3)山崎城跡 国府町廣瀬
4)白米城跡 国府町蓑輪
5)梨打城跡 国府町漆垣内
6)光寿庵砦跡 国府町上広瀬
7)ウシロゴ砦跡 国府町宇津江
8)唐松砦跡 国府町宇津江
9)須代山砦跡 国府町宇津江
10)城洞砦跡 国府町宇津江
11)長洞砦跡 国府町宇津江
12)寺洞城塞群 国府町瓜巣・名張
13)沢上砦跡 国府町金桶
14)小洞砦跡 国府町瓜巣
15)土洞砦跡 国府町瓜巣
16)志を洞砦跡 国府町瓜巣
17)鴻の岩砦跡 国府町廣瀬
18)中山砦跡 国府町廣瀬
19)陣ヶ洞砦跡 国府町廣瀬
20)牛追砦跡 国府町蓑輪
21)境の峰砦跡 国府町廣瀬
22)甲山城跡 国府町上広瀬
23)和田砦跡 国府町山本
24)清峯寺平砦跡 国府町山本
25)大洞砦跡 国府町鶴巣
26)西門前砦跡 国府町西門前
山岳寺院
27)清峯寺 国府町鶴巣
28)安養寺・安寧寺跡 国府町半田
今回、パネル展示では、下記の飛騨の山城についても展示をしております。
飛騨の著名な山城
<高山地区>
1)高山城跡 高山市城山 (県指定史跡)
2)松倉城跡 高山市西之一色町 (県指定史跡)
<古川地区>
3)小島城跡 飛騨市古川町太江 (県指定史跡)
4)向小島城跡 飛騨市古川町笹が洞 (県指定史跡)
5)小鷹利城跡 飛騨市古川町黒内 (県指定史跡)
6)蛤城跡 飛騨市古川町高野 (県指定史跡)
<萩原地区>
7)萩原諏訪城跡 下呂市萩原町萩原(下呂市指定史跡)
8)桜洞城跡 下呂市萩原町桜洞(平成23年に発掘調査)
<荘川地区>
9)牧戸城跡 高山市荘川町牧戸(平成23年に新発見)
<神岡地区>
10)高原諏訪城跡 飛騨市神岡町和佐保 (国指定史跡)
展示期間は7月10日~8月10日頃の予定です。
こくふさくらホール ロビーにて、展示を行ないます。
徳積善太








