10月1日放送分_応永飛騨の乱について_講演会より
(10月1日放送分 第169回)みなさんこんにちは、飛騨の歴史再発見のコーナーです。
このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号 わたくし長瀬公昭がお届けしてまいります。
先週あたりから急に寒くなりましたよね。思えば、先月の1日は暑くて暑くて仕方が
なかったことを思い出します。
ついこの前の事なんですが、ずいぶん前の事のように思いますよね。今になって思い
起こせば、9月13日ごろに台風が来て大雨が降り、一気に涼しくなりました。10日ほど
で一気に気温が下がり、厚さ寒さも彼岸までという言葉の通り、お彼岸の23日を過ぎ
る頃には、もう秋風が吹くようになりました。気がつけばもう10月に入りましたが、
今年もあっという間に過ぎて行きましたね。
先月まで、私は応永飛騨の乱600年祭というイベントを企画して、大変忙しい日々
を過ごしてまいりました。先月はメインイベントである展覧会と600回忌法要、
そして記念講演会を企画して、姉小路氏と廣瀬氏についてたくさんの皆様にご紹介
してまいりました。ご覧いただいた方もあろうかと思いますが、ご協力をいただき
ましてありがとうございました。後は、そのイベントの最終仕上げとして、本の出版
が残っておりますが、現在、校正作業に入っております。のべ25人の皆さんの研究
の執筆と、今回のイベントの概要。姉小路氏や廣瀬氏にゆかりの地などを盛り込んで、
総ページ数300ページにまとめてあります。
300ページの本を造るとなるとなかなか時間もかかりますし、正確性を期すために、
何度も校正が必要です。今のところ、今月末に発行できると思いますので、頑張って
おります。出版できるようになりましたら、またこの番組でもお知らせいたします
ので、よろしくお願いいたします。
さて、本日の放送に移りましょう。今日の放送は、姉小路氏と廣瀬氏について、
去る9月23日に高山市民文化会館の小ホールにて記念講演会を行いました。
慶應義塾大学文学部の准教授の小川剛生先生と、非常勤講師の大薮海先生に御講演
をいただきました。本日は、その時の内容から、新しく分った事についてお話し
したいと思います。

当日は、午後1時から、両先生の記念講演がそれぞれ1時間づつありまして、
大薮海先生には、「応永飛騨の乱 その虚像と実像」というテーマで。
小川剛生先生には、「姉小路基綱の和歌について」というテーマでお話しいただき
ました。
会場には歴史ファンから地元のゆかりの地の皆様、熱心な研究者に至るまで、沢山の
皆さんにお越しいただきましたが、当日お見えにならなかった皆様のために、特別に
かいつまんでこの放送でご紹介したいと思います。

まず、大薮海先生には、応永飛騨の乱がなぜ起こったかについて最新の研究をもとに
お話しいただきました。その中で、姉小路氏の始まりについて、お話し下さいました。
先生のお話しをする前に、ちょっとその時期の事について振り返ってみたいと思います。
そもそも、姉小路氏が飛騨とかかわりを持ったのは、姉小路家綱という人が最終的には
従三位参議に任ぜられた、公家でも上流階級の人だったわけですが、その人が飛騨国司
として活躍したということに由来します。当時は、後醍醐天皇により建武の新政が始め
られ、120代以上続く日本の天皇陛下の歴史の中でも南朝と北朝に分かれた非常に
複雑な時代でした。
つまり、2つの政府が日本の中に存在した時代です。国司姉小路氏は、南朝方、つまり
後醍醐天皇によって飛騨国司に任ぜられましたが、実は、国司として任ぜられた公家は、
3つしかありませんでした。さらに、北朝は、時の足利尊氏によって樹立されていました
から、守護というものを置いて、武家が国の管理を進めました。そのため、飛騨守護
としては、京極氏がその任にあたるという状態でした。
したがって、飛騨には二つの領主が存在したことになります。
つまり、南朝方からは国司として姉小路氏。北朝方からは守護として京極氏という武家が
管理していたという時代です。そういう混迷の時代であったという事を頭に入れておいて
ください。大薮先生のお話しは後半でお話ししたいと思います。
ちょっとここでブレイクしましょう。
曲は「山口百恵 秋桜(コスモス)」をお届けします。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本日の飛騨の歴史再発見は、姉小路と廣瀬講演会の内容についてお話ししています。
さて、前半では、室町時代に姉小路氏が国司に補任(ぶにん)されたときの背景に
ついてご紹介しましたが、実は、研究者の間でも、姉小路家綱がいったいいつ飛騨
国司になったのかということがわかりませんでした。今まで一般的に言われてきた
のは、先ほどお話しした後醍醐天皇が建武の新政を行った前後、つまり鎌倉幕府が
滅んだのが、高校の授業で「一味さんざん北条氏」っていう語呂で覚えたと思います
が、1333年頃です。
ただし、建武という時代は3年しかありませんでしたので、1333年から1335年だと
考えられていました。
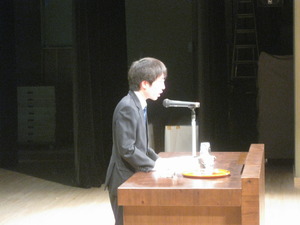
ただし、家綱の年齢からすると不自然な部分があって、その証拠がありませんでした。
今回、大薮先生は、史料を提示されながら、
「家綱はもともと北朝に仕えていた時期があり、それが貞和4年(1348)。その後、
貞治2年(1363)に北朝から役職を解かれたことが分かったという事でした。今迄の
地元の史料では、姉小路家は南朝に仕えていたとされていましたから、最初は
北朝で、その後に南朝になったという記述が発見されたということになります。
したがって、飛騨国司として補任された時期は、今までの説1335年よりも少なくとも
1363年以降という形になり、28年の差がわかったということです。
また、廣瀬氏については、応安5年(1372)に廣瀬氏の名前が史料に見え、江名子・
松橋という場所。これは、高山市の江名子と上岡本近辺にあった松橋という所領の
事ですが、そこを公家の山科家が持っていました。
その所領を守護京極氏の被官である垣見氏が押領していたため、幕府より保全を
命ぜられたのが廣瀬左近将監と江馬但馬四郎だったということです。
幕府から直接命令を受けることができるほどの立場にあった一族であったことを
提示されました。
その後、応永18年(1411)に応永飛騨の乱が起るわけですが、そもそもの原因に
ついて今まで地元の研究者や多賀秋五郎氏は、先ほど申し上げた江名子・松橋郷
という場所が、山科家の所領であったのに、いつしか押領されていたというもの
でした。
ところが大藪先生は、この乱の原因が、飛騨という一地方の所領問題に端を発する
ものではなくて、斯波義将(よしまさ)が絡んだものであると指摘されました。
つまり、山科家が、飛騨に家来を送って調査したところ、自分の領地だと思って
いた江名子と松橋が、いつしか、姉小路まさ綱が所有していて、彼は斯波氏から
預かった所領であると主張したために、山科家との確執が強まりました。
その後、斯波義将が亡くなり、尹綱が斯波氏の後ろ盾を失い、おまけに斯波氏を
庇護していた3代将軍足利義満も亡くなって、次の将軍義持がその斯波氏の勢力を
抑制したことがきっかけとなったという事を発表されました。
つまり、応永飛騨の乱は、一地方の土地争いではなくて、斯波氏勢力の削減という
将軍義持の意向が大きく左右したということがあったのではないかという説を発表
されたのです。
また、応永飛騨の乱について、史料に基づいて説明されました。
・姉小路尹綱が幕府によって討伐されたこと。
・廣瀬氏は父親の常登が尹綱方。子の徳静が守護方という風に、親子に分かれて戦ったこと。
・姉小路尹綱は、最終的に守護京極氏の家臣である赤穴弘行に討たれたということ
を説明されました。
また、先生は史料を使って、乱の後のことも説明されました。
・廣瀬氏が広瀬郷をめぐって醍醐寺と訴訟を繰り返しながらも、戦国時代まで生き延びたこと。
・姉小路小島家は、師言という人が、将軍から一字をもらったりして、幕府との密接な関係が
あった事。
・尹綱の遺児尹家は、古川家の代表として、後に正三位参議にまでなるという、異例の出世を
することを説明されました。
今日、ご紹介しました内容は、専門的な名前がたくさん出てきましたので、少し難し
かったかもしれませんが、とても勉強になる講演会でした。私もいろいろと勉強して
まいりましたが、今までの論説とは異なり、新しく中世の飛騨にメスを入れた形になった
と思いました。
さて、本日も時間となりました。
来週は、本日、小川先生のお話しされた内容に触れることができませんでしたので、
小川先生のお話しされた「姉小路基綱の和歌」についてのお話しをしたいと思います。
今日は、この曲でお別れしたいと思います。
曲の方は、「松崎しげる ワンダフルモーメント」をお届けします。
ではまた来週、お会いしましょう!
徳積善太
このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号 わたくし長瀬公昭がお届けしてまいります。
先週あたりから急に寒くなりましたよね。思えば、先月の1日は暑くて暑くて仕方が
なかったことを思い出します。
ついこの前の事なんですが、ずいぶん前の事のように思いますよね。今になって思い
起こせば、9月13日ごろに台風が来て大雨が降り、一気に涼しくなりました。10日ほど
で一気に気温が下がり、厚さ寒さも彼岸までという言葉の通り、お彼岸の23日を過ぎ
る頃には、もう秋風が吹くようになりました。気がつけばもう10月に入りましたが、
今年もあっという間に過ぎて行きましたね。
先月まで、私は応永飛騨の乱600年祭というイベントを企画して、大変忙しい日々
を過ごしてまいりました。先月はメインイベントである展覧会と600回忌法要、
そして記念講演会を企画して、姉小路氏と廣瀬氏についてたくさんの皆様にご紹介
してまいりました。ご覧いただいた方もあろうかと思いますが、ご協力をいただき
ましてありがとうございました。後は、そのイベントの最終仕上げとして、本の出版
が残っておりますが、現在、校正作業に入っております。のべ25人の皆さんの研究
の執筆と、今回のイベントの概要。姉小路氏や廣瀬氏にゆかりの地などを盛り込んで、
総ページ数300ページにまとめてあります。
300ページの本を造るとなるとなかなか時間もかかりますし、正確性を期すために、
何度も校正が必要です。今のところ、今月末に発行できると思いますので、頑張って
おります。出版できるようになりましたら、またこの番組でもお知らせいたします
ので、よろしくお願いいたします。
さて、本日の放送に移りましょう。今日の放送は、姉小路氏と廣瀬氏について、
去る9月23日に高山市民文化会館の小ホールにて記念講演会を行いました。
慶應義塾大学文学部の准教授の小川剛生先生と、非常勤講師の大薮海先生に御講演
をいただきました。本日は、その時の内容から、新しく分った事についてお話し
したいと思います。
当日は、午後1時から、両先生の記念講演がそれぞれ1時間づつありまして、
大薮海先生には、「応永飛騨の乱 その虚像と実像」というテーマで。
小川剛生先生には、「姉小路基綱の和歌について」というテーマでお話しいただき
ました。
会場には歴史ファンから地元のゆかりの地の皆様、熱心な研究者に至るまで、沢山の
皆さんにお越しいただきましたが、当日お見えにならなかった皆様のために、特別に
かいつまんでこの放送でご紹介したいと思います。
まず、大薮海先生には、応永飛騨の乱がなぜ起こったかについて最新の研究をもとに
お話しいただきました。その中で、姉小路氏の始まりについて、お話し下さいました。
先生のお話しをする前に、ちょっとその時期の事について振り返ってみたいと思います。
そもそも、姉小路氏が飛騨とかかわりを持ったのは、姉小路家綱という人が最終的には
従三位参議に任ぜられた、公家でも上流階級の人だったわけですが、その人が飛騨国司
として活躍したということに由来します。当時は、後醍醐天皇により建武の新政が始め
られ、120代以上続く日本の天皇陛下の歴史の中でも南朝と北朝に分かれた非常に
複雑な時代でした。
つまり、2つの政府が日本の中に存在した時代です。国司姉小路氏は、南朝方、つまり
後醍醐天皇によって飛騨国司に任ぜられましたが、実は、国司として任ぜられた公家は、
3つしかありませんでした。さらに、北朝は、時の足利尊氏によって樹立されていました
から、守護というものを置いて、武家が国の管理を進めました。そのため、飛騨守護
としては、京極氏がその任にあたるという状態でした。
したがって、飛騨には二つの領主が存在したことになります。
つまり、南朝方からは国司として姉小路氏。北朝方からは守護として京極氏という武家が
管理していたという時代です。そういう混迷の時代であったという事を頭に入れておいて
ください。大薮先生のお話しは後半でお話ししたいと思います。
ちょっとここでブレイクしましょう。
曲は「山口百恵 秋桜(コスモス)」をお届けします。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本日の飛騨の歴史再発見は、姉小路と廣瀬講演会の内容についてお話ししています。
さて、前半では、室町時代に姉小路氏が国司に補任(ぶにん)されたときの背景に
ついてご紹介しましたが、実は、研究者の間でも、姉小路家綱がいったいいつ飛騨
国司になったのかということがわかりませんでした。今まで一般的に言われてきた
のは、先ほどお話しした後醍醐天皇が建武の新政を行った前後、つまり鎌倉幕府が
滅んだのが、高校の授業で「一味さんざん北条氏」っていう語呂で覚えたと思います
が、1333年頃です。
ただし、建武という時代は3年しかありませんでしたので、1333年から1335年だと
考えられていました。
ただし、家綱の年齢からすると不自然な部分があって、その証拠がありませんでした。
今回、大薮先生は、史料を提示されながら、
「家綱はもともと北朝に仕えていた時期があり、それが貞和4年(1348)。その後、
貞治2年(1363)に北朝から役職を解かれたことが分かったという事でした。今迄の
地元の史料では、姉小路家は南朝に仕えていたとされていましたから、最初は
北朝で、その後に南朝になったという記述が発見されたということになります。
したがって、飛騨国司として補任された時期は、今までの説1335年よりも少なくとも
1363年以降という形になり、28年の差がわかったということです。
また、廣瀬氏については、応安5年(1372)に廣瀬氏の名前が史料に見え、江名子・
松橋という場所。これは、高山市の江名子と上岡本近辺にあった松橋という所領の
事ですが、そこを公家の山科家が持っていました。
その所領を守護京極氏の被官である垣見氏が押領していたため、幕府より保全を
命ぜられたのが廣瀬左近将監と江馬但馬四郎だったということです。
幕府から直接命令を受けることができるほどの立場にあった一族であったことを
提示されました。
その後、応永18年(1411)に応永飛騨の乱が起るわけですが、そもそもの原因に
ついて今まで地元の研究者や多賀秋五郎氏は、先ほど申し上げた江名子・松橋郷
という場所が、山科家の所領であったのに、いつしか押領されていたというもの
でした。
ところが大藪先生は、この乱の原因が、飛騨という一地方の所領問題に端を発する
ものではなくて、斯波義将(よしまさ)が絡んだものであると指摘されました。
つまり、山科家が、飛騨に家来を送って調査したところ、自分の領地だと思って
いた江名子と松橋が、いつしか、姉小路まさ綱が所有していて、彼は斯波氏から
預かった所領であると主張したために、山科家との確執が強まりました。
その後、斯波義将が亡くなり、尹綱が斯波氏の後ろ盾を失い、おまけに斯波氏を
庇護していた3代将軍足利義満も亡くなって、次の将軍義持がその斯波氏の勢力を
抑制したことがきっかけとなったという事を発表されました。
つまり、応永飛騨の乱は、一地方の土地争いではなくて、斯波氏勢力の削減という
将軍義持の意向が大きく左右したということがあったのではないかという説を発表
されたのです。
また、応永飛騨の乱について、史料に基づいて説明されました。
・姉小路尹綱が幕府によって討伐されたこと。
・廣瀬氏は父親の常登が尹綱方。子の徳静が守護方という風に、親子に分かれて戦ったこと。
・姉小路尹綱は、最終的に守護京極氏の家臣である赤穴弘行に討たれたということ
を説明されました。
また、先生は史料を使って、乱の後のことも説明されました。
・廣瀬氏が広瀬郷をめぐって醍醐寺と訴訟を繰り返しながらも、戦国時代まで生き延びたこと。
・姉小路小島家は、師言という人が、将軍から一字をもらったりして、幕府との密接な関係が
あった事。
・尹綱の遺児尹家は、古川家の代表として、後に正三位参議にまでなるという、異例の出世を
することを説明されました。
今日、ご紹介しました内容は、専門的な名前がたくさん出てきましたので、少し難し
かったかもしれませんが、とても勉強になる講演会でした。私もいろいろと勉強して
まいりましたが、今までの論説とは異なり、新しく中世の飛騨にメスを入れた形になった
と思いました。
さて、本日も時間となりました。
来週は、本日、小川先生のお話しされた内容に触れることができませんでしたので、
小川先生のお話しされた「姉小路基綱の和歌」についてのお話しをしたいと思います。
今日は、この曲でお別れしたいと思います。
曲の方は、「松崎しげる ワンダフルモーメント」をお届けします。
ではまた来週、お会いしましょう!
徳積善太


