平成25年3月22日放送分_まつりの森の屋台について3
(平成25年3月22日放送分 第286回)みなさんこんにちは。飛騨の歴史再発見のコーナーです。
このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。
先日、昨年国府で行いました国府山城フォーラムで講演していただきました山城研究家の佐伯哲也
先生からご連絡をいただきました。「長瀬さん、このほど学研から出版された『歴史群像』という雑誌に、
高山の松倉城のことを書きましたのでご覧ください。」ということでした。
早速、内容を拝見しましたら、おそらく本邦初公開でしょう、松倉城の想像図が2ページにわたって
描かれていました。
今迄、高山城については、森洞春さんなど画家の皆さんが描かれていましたが、佐伯さんが調査
された内容に基づいて、かなり正確に記されております。このイラストによりますと、松倉城の天守閣は
半地下式の2層3重構造になっていて、その下のところに本丸の天守閣を巻くようにぐるりと外曲輪が
ひろがっています。もちろんその土塀の下には、現在残されている石垣がつづいています。
その下の三の丸のところには、単層の櫓があって、そこが搦め手になっています。屋根はすべて
桧皮葺になっています。以前、この放送でもお話しした事がありますが、15年ほど前までは、松倉城
と言えば、天正11年に飛騨を統一した三木自綱の造った城であると言う説が定説となっていました。
ところが、最近の研究では、石垣の城と言うもの自体が、天正6年に織田信長が滋賀県の安土に
造った安土城以降に、信長の家臣たちによって権威の象徴として全国に広まったという説が提唱
されました。つまり、石垣の上部に造られる構造物も、土塀など鉄砲を考慮した建造物に替わって
いき、重量も重くかかる様になった。そのため、石垣の裏側には裏込め石という細かい石を入れる
ことで石垣そのものの耐久性を増加させ、排水もよくするという構造物に変って行ったという変遷が
あります。
したがって、現在残る石垣は、三木氏時代の物ではなくて、金森氏時代に造られたもの。
それも、石垣の構造や石そのものの形態などから天正14年~天正20年の間に造られたのではなか
ろうかというお話しです。
この松倉城については、今回の佐伯先生の発表をもとに、この放送でも特集を組んでみたいと思います
が、大変興味深い絵図ですので、一度皆さんも御覧になってはいかがでしょうか。
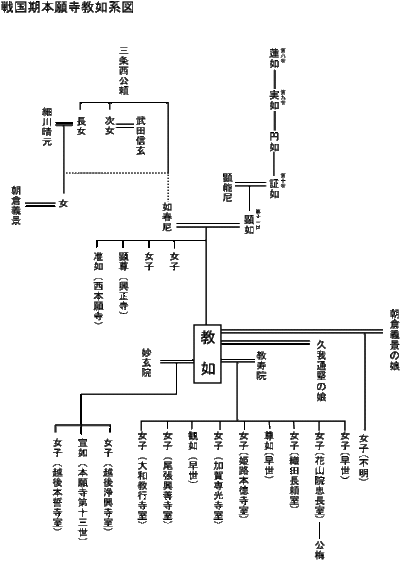
話は変りますが、以前の放送でお伝えしましたように、来月4月2日~8日まで、浄土真宗の東本願寺で
「教如上人400回忌記念法要」が営まれます。私も嘉念坊善俊顕彰会の旅行で3日に京都東本願寺まで
行く予定ですが、今年、高山別院でも「教如上人法要と展覧会」を開催することになりました。
10月5日の教如上人の御命日に法要が高山別院で営まれ、その際に高山別院の宝物館を改装して、
飛騨と教如上人、そして高山城主だった金森長近との関係について展示を行います。
織田信長との10年間にわたる石山本願寺の戦いの後、11代顕如上人は、信長と和睦して鷺宮に
本願寺を移します。しかしそれに不服を持った長男の教如上人は、石山本願寺に残り徹底抗戦を
します。最終的には和睦して紀州の雑賀に隠れました。
その後、本願寺の12世として君臨しますが、顕如の妻であり教如の母である如春尼から、「顕如の
遺言があり本願寺の12世は弟の准如とする」という話を豊臣秀吉にします。秀吉は教如を本願寺
12世の職から解き、弟の准如上人が12世となりました。
教如上人は9年間にわたり放浪されました。今迄そのことを調査してまいりましたが、郡上市和良町
気良や、越前大野市の南専寺、越中五箇山にも教如上人が滞在したと言われる伝承の場所がある
ことがわかりました。

当然、その場所を行き来する時には、白川郷の中野照蓮寺にも滞在されたようです。
そういったことや、茶会記などには金森長近とたびたび茶の湯を嗜んでいた事。関ヶ原の戦いの翌週
には、徳川家康の大津の陣に、長近が教如を招いて家康と会談させている事。それがやがて今日の
本願寺派と大谷派の東西両立になったと言う事。
そして、高山のまちづくりにおいては、江名子川と宮川の内側に浄土真宗の寺院、その外側には他宗派
の寺院が配置して金森氏が留守の間に高山の町を浄土真宗に守らせていたので、秀吉から本尊阿弥陀
如来立像を賜ったと言う話があることなどがあります。
高山の町いや、飛騨の国とその城主金森氏が、浄土真宗大谷派の開祖教如上人と物凄くかかわりが
深かったと言うことを証明する初めての展示となると思います。一般公開は10月5日からの予定ですが、
またこの放送でも詳しくお知らせいたしますので、どうぞご期待下さい。
なお、4月3日の東本願寺の旅行につきましてはまだ余裕があるようです。行ってみたいなという方は、
高山別院までお問い合わせください。今週はニュースが多くて、すでに前半部分の時間を使ってしまい
ました。後半では、予定しておりました今週の放送、「高山祭りの森の屋台について パート3」今週は、
福寿台と力神台についてお話したいと思います。
ちょっとここでブレイクしましょう。曲の方は、「 」をお届けします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さて、本日の放送に入りましょう。
本日の放送は、第四週ですので屋台の話。先先月から続けてお話ししております、まつりの森の屋台
についてお話ししたと思います。
まつりの森には8台の屋台がありますが、先月までに、4台の屋台をご紹介しました。
神楽台、臥龍台、金鶏台、そして飛騨の屋台で最大の金時台の4台でした。今日ご紹介しますのは、
福寿台と相撲をテーマにした力神台をご紹介します。

まず、福寿台ですが、この屋台は、まつりの森の平成屋台の6番目として作られました。
平成8年(1996)3月より着手し、翌平成9年の10月末まで1年七カ月の歳月をかけて作られました。
この屋台のテーマは日本人に大変親しまれている七福神。下段彫刻、中段胴幕、見送り幕など、
各所に七福神をモチーフにした作品が施してあります。大きさは、全長4.1m、幅2.4m、高さ最高で
7.58mなどとなっており、大きさとしては大体、高山祭りの屋台と同じくらいの大きさです。
下段と中段の白木彫刻は、井波の彫刻師 山田耕運さん永富伸一さんや、飛騨の彫刻師東勝廣さん、
元田木山さん、若林繁夫さんらが手分けして作られた作品で、それぞれの特徴が良く出ている結晶体
です。
ところで七福神と言いますが、皆さん、7人の神様のお名前を全部言えますでしょうか。
7人すべて言えると言う方は相当な信者の方か、相当お詳しい方だと思います。
私も、原稿を書くにあたってすべて言えるかなと思いましたが、やっぱり言えませんでした。
七福神は、おなかの大きな布袋様。打ち出の小槌を持った大黒様。頭のおでこの長い福禄寿様。
釣竿を持った恵比寿様。ここまでは、高山の屋台の名前にもなっていますから、すぐ出てきました。
そして唯一の女性の弁天様までは、何とか云えました。
あと2つはインドの神様毘沙門天様と素老人です。
それぞれの神様について、ちょっとお話しますと、
・布袋さまは、唐の末期の明州(現在の中国浙江省寧波市)に実在したといわれる仏教のお坊さんなん
ですね。
・大黒天様は、インドのヒンドゥー教のシヴァ神の化身マハーカーラ神。日本古来の大国主命の習合。
大黒柱と現されるように食物・財福を司る神となったそうです。
・恵比寿さまは、古くは「大漁追福」の漁業の神です。時代と共に福の神として「商売繁盛」や「五穀豊穣」
をもたらす、商業や農業の神となった。唯一日本由来の神様なんだそうです。
・福禄寿様は、道教の宋の道士天南星、または、道教の神で南極星の化身の南極老人。
寿老人と同一神ともされるそうです。先ほど、屋台と関係あると言いましたが、古川の青龍台に乗っている
からくり人形がこの福禄寿です。
・弁才天 (弁財天)弁天様は七福神の中の紅一点=女性で元はインドのヒンドゥー教の女神であるサラス
ヴァティー神です。七福神の一柱としては「弁財天」と「財産の財の字」で表記されることが多いそうです。
・毘沙門天様は、元はインドのヒンドゥー教のクベーラ神。仏教に取り入れられ日本では毘沙門天
(ヴァイシュラヴァナ)と呼ばれるようになりました。
・最後の寿老人さまは、道教の神様で南極星の化身の南極老人のことを指すそうです。

さて、続いて力神車についてですが、この屋台の台名は、飛騨には皆無ですが、実は半田など知多や
尾張の山車に多く取り入れられています。まつりの森の力神台は日本書紀にある大和の国の豪傑
「当麻蹴速(とうまけりはや)」と出雲の国の強者「野見宿弥」(のみのすくね)が、今から1300年間の
7月7日に力比べをしたことが、現在の日本の相撲の起源とされているということで、屋台のモチーフ
として採用されたようです。
そのため、彫刻を始め、見送り、金具等屋台のいたるところに相撲に因んだ装飾が施されています。
屋台そのものの大きさは、全長4.44m高さ最高で7.92mと高山祭りの屋台とほぼ同じ大きさですが、
この屋台は、他の屋台に比べて、地元の工匠の皆さんがより多く関わっておられます。
大工は八野明さんをはじめとする八野大工の皆さん。彫刻には、上段欄間には高山の若林繁雄さんや
屋根飾りには東勝廣さんの作品が採用されています。
そして、車輪は輪締めといって丸く切った木を
外側から鉄の輪っかを焼いてはめ込み、はまったところへ大量の水をかけて一気に締めると言う方法で
作られています。これには、飛騨の新名鍛冶屋さんと田中鉄工さんが関わって造られています。
また、屋台中段の幕は、他の屋台と異なり、青い幕が採用され、そこに描かれた錦絵には、飛騨白川出身
の相撲取り、白真弓関が描かれています。
相撲尽くしの力強い屋台ですので、一度まつりの森でご覧ください。
さて、本日も時間となりました。来週は今月が5週ありますのでお休みをいただきます。
皆様には4月の第一週でお会いしたいと思います。次回の放送は、高山祭りの前ですのでまつりに因んだ
お話し、飛騨の雅楽のお話しをお届けしたいと思います。どうぞお楽しみになさってください。
それでは本日はこの曲でお別れです。
曲の方は「 」をお届けします。それではまたさ来週お会いしましょう。
徳積善太
このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。
先日、昨年国府で行いました国府山城フォーラムで講演していただきました山城研究家の佐伯哲也
先生からご連絡をいただきました。「長瀬さん、このほど学研から出版された『歴史群像』という雑誌に、
高山の松倉城のことを書きましたのでご覧ください。」ということでした。
早速、内容を拝見しましたら、おそらく本邦初公開でしょう、松倉城の想像図が2ページにわたって
描かれていました。
今迄、高山城については、森洞春さんなど画家の皆さんが描かれていましたが、佐伯さんが調査
された内容に基づいて、かなり正確に記されております。このイラストによりますと、松倉城の天守閣は
半地下式の2層3重構造になっていて、その下のところに本丸の天守閣を巻くようにぐるりと外曲輪が
ひろがっています。もちろんその土塀の下には、現在残されている石垣がつづいています。
その下の三の丸のところには、単層の櫓があって、そこが搦め手になっています。屋根はすべて
桧皮葺になっています。以前、この放送でもお話しした事がありますが、15年ほど前までは、松倉城
と言えば、天正11年に飛騨を統一した三木自綱の造った城であると言う説が定説となっていました。
ところが、最近の研究では、石垣の城と言うもの自体が、天正6年に織田信長が滋賀県の安土に
造った安土城以降に、信長の家臣たちによって権威の象徴として全国に広まったという説が提唱
されました。つまり、石垣の上部に造られる構造物も、土塀など鉄砲を考慮した建造物に替わって
いき、重量も重くかかる様になった。そのため、石垣の裏側には裏込め石という細かい石を入れる
ことで石垣そのものの耐久性を増加させ、排水もよくするという構造物に変って行ったという変遷が
あります。
したがって、現在残る石垣は、三木氏時代の物ではなくて、金森氏時代に造られたもの。
それも、石垣の構造や石そのものの形態などから天正14年~天正20年の間に造られたのではなか
ろうかというお話しです。
この松倉城については、今回の佐伯先生の発表をもとに、この放送でも特集を組んでみたいと思います
が、大変興味深い絵図ですので、一度皆さんも御覧になってはいかがでしょうか。
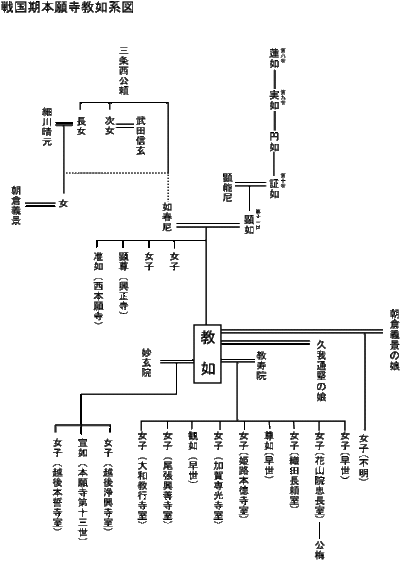
話は変りますが、以前の放送でお伝えしましたように、来月4月2日~8日まで、浄土真宗の東本願寺で
「教如上人400回忌記念法要」が営まれます。私も嘉念坊善俊顕彰会の旅行で3日に京都東本願寺まで
行く予定ですが、今年、高山別院でも「教如上人法要と展覧会」を開催することになりました。
10月5日の教如上人の御命日に法要が高山別院で営まれ、その際に高山別院の宝物館を改装して、
飛騨と教如上人、そして高山城主だった金森長近との関係について展示を行います。
織田信長との10年間にわたる石山本願寺の戦いの後、11代顕如上人は、信長と和睦して鷺宮に
本願寺を移します。しかしそれに不服を持った長男の教如上人は、石山本願寺に残り徹底抗戦を
します。最終的には和睦して紀州の雑賀に隠れました。
その後、本願寺の12世として君臨しますが、顕如の妻であり教如の母である如春尼から、「顕如の
遺言があり本願寺の12世は弟の准如とする」という話を豊臣秀吉にします。秀吉は教如を本願寺
12世の職から解き、弟の准如上人が12世となりました。
教如上人は9年間にわたり放浪されました。今迄そのことを調査してまいりましたが、郡上市和良町
気良や、越前大野市の南専寺、越中五箇山にも教如上人が滞在したと言われる伝承の場所がある
ことがわかりました。

当然、その場所を行き来する時には、白川郷の中野照蓮寺にも滞在されたようです。
そういったことや、茶会記などには金森長近とたびたび茶の湯を嗜んでいた事。関ヶ原の戦いの翌週
には、徳川家康の大津の陣に、長近が教如を招いて家康と会談させている事。それがやがて今日の
本願寺派と大谷派の東西両立になったと言う事。
そして、高山のまちづくりにおいては、江名子川と宮川の内側に浄土真宗の寺院、その外側には他宗派
の寺院が配置して金森氏が留守の間に高山の町を浄土真宗に守らせていたので、秀吉から本尊阿弥陀
如来立像を賜ったと言う話があることなどがあります。
高山の町いや、飛騨の国とその城主金森氏が、浄土真宗大谷派の開祖教如上人と物凄くかかわりが
深かったと言うことを証明する初めての展示となると思います。一般公開は10月5日からの予定ですが、
またこの放送でも詳しくお知らせいたしますので、どうぞご期待下さい。
なお、4月3日の東本願寺の旅行につきましてはまだ余裕があるようです。行ってみたいなという方は、
高山別院までお問い合わせください。今週はニュースが多くて、すでに前半部分の時間を使ってしまい
ました。後半では、予定しておりました今週の放送、「高山祭りの森の屋台について パート3」今週は、
福寿台と力神台についてお話したいと思います。
ちょっとここでブレイクしましょう。曲の方は、「 」をお届けします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さて、本日の放送に入りましょう。
本日の放送は、第四週ですので屋台の話。先先月から続けてお話ししております、まつりの森の屋台
についてお話ししたと思います。
まつりの森には8台の屋台がありますが、先月までに、4台の屋台をご紹介しました。
神楽台、臥龍台、金鶏台、そして飛騨の屋台で最大の金時台の4台でした。今日ご紹介しますのは、
福寿台と相撲をテーマにした力神台をご紹介します。

まず、福寿台ですが、この屋台は、まつりの森の平成屋台の6番目として作られました。
平成8年(1996)3月より着手し、翌平成9年の10月末まで1年七カ月の歳月をかけて作られました。
この屋台のテーマは日本人に大変親しまれている七福神。下段彫刻、中段胴幕、見送り幕など、
各所に七福神をモチーフにした作品が施してあります。大きさは、全長4.1m、幅2.4m、高さ最高で
7.58mなどとなっており、大きさとしては大体、高山祭りの屋台と同じくらいの大きさです。
下段と中段の白木彫刻は、井波の彫刻師 山田耕運さん永富伸一さんや、飛騨の彫刻師東勝廣さん、
元田木山さん、若林繁夫さんらが手分けして作られた作品で、それぞれの特徴が良く出ている結晶体
です。
ところで七福神と言いますが、皆さん、7人の神様のお名前を全部言えますでしょうか。
7人すべて言えると言う方は相当な信者の方か、相当お詳しい方だと思います。
私も、原稿を書くにあたってすべて言えるかなと思いましたが、やっぱり言えませんでした。
七福神は、おなかの大きな布袋様。打ち出の小槌を持った大黒様。頭のおでこの長い福禄寿様。
釣竿を持った恵比寿様。ここまでは、高山の屋台の名前にもなっていますから、すぐ出てきました。
そして唯一の女性の弁天様までは、何とか云えました。
あと2つはインドの神様毘沙門天様と素老人です。
それぞれの神様について、ちょっとお話しますと、
・布袋さまは、唐の末期の明州(現在の中国浙江省寧波市)に実在したといわれる仏教のお坊さんなん
ですね。
・大黒天様は、インドのヒンドゥー教のシヴァ神の化身マハーカーラ神。日本古来の大国主命の習合。
大黒柱と現されるように食物・財福を司る神となったそうです。
・恵比寿さまは、古くは「大漁追福」の漁業の神です。時代と共に福の神として「商売繁盛」や「五穀豊穣」
をもたらす、商業や農業の神となった。唯一日本由来の神様なんだそうです。
・福禄寿様は、道教の宋の道士天南星、または、道教の神で南極星の化身の南極老人。
寿老人と同一神ともされるそうです。先ほど、屋台と関係あると言いましたが、古川の青龍台に乗っている
からくり人形がこの福禄寿です。
・弁才天 (弁財天)弁天様は七福神の中の紅一点=女性で元はインドのヒンドゥー教の女神であるサラス
ヴァティー神です。七福神の一柱としては「弁財天」と「財産の財の字」で表記されることが多いそうです。
・毘沙門天様は、元はインドのヒンドゥー教のクベーラ神。仏教に取り入れられ日本では毘沙門天
(ヴァイシュラヴァナ)と呼ばれるようになりました。
・最後の寿老人さまは、道教の神様で南極星の化身の南極老人のことを指すそうです。

さて、続いて力神車についてですが、この屋台の台名は、飛騨には皆無ですが、実は半田など知多や
尾張の山車に多く取り入れられています。まつりの森の力神台は日本書紀にある大和の国の豪傑
「当麻蹴速(とうまけりはや)」と出雲の国の強者「野見宿弥」(のみのすくね)が、今から1300年間の
7月7日に力比べをしたことが、現在の日本の相撲の起源とされているということで、屋台のモチーフ
として採用されたようです。
そのため、彫刻を始め、見送り、金具等屋台のいたるところに相撲に因んだ装飾が施されています。
屋台そのものの大きさは、全長4.44m高さ最高で7.92mと高山祭りの屋台とほぼ同じ大きさですが、
この屋台は、他の屋台に比べて、地元の工匠の皆さんがより多く関わっておられます。
大工は八野明さんをはじめとする八野大工の皆さん。彫刻には、上段欄間には高山の若林繁雄さんや
屋根飾りには東勝廣さんの作品が採用されています。
そして、車輪は輪締めといって丸く切った木を
外側から鉄の輪っかを焼いてはめ込み、はまったところへ大量の水をかけて一気に締めると言う方法で
作られています。これには、飛騨の新名鍛冶屋さんと田中鉄工さんが関わって造られています。
また、屋台中段の幕は、他の屋台と異なり、青い幕が採用され、そこに描かれた錦絵には、飛騨白川出身
の相撲取り、白真弓関が描かれています。
相撲尽くしの力強い屋台ですので、一度まつりの森でご覧ください。
さて、本日も時間となりました。来週は今月が5週ありますのでお休みをいただきます。
皆様には4月の第一週でお会いしたいと思います。次回の放送は、高山祭りの前ですのでまつりに因んだ
お話し、飛騨の雅楽のお話しをお届けしたいと思います。どうぞお楽しみになさってください。
それでは本日はこの曲でお別れです。
曲の方は「 」をお届けします。それではまたさ来週お会いしましょう。
徳積善太


